産婦人科教室に入局して6年目の10月、私は留萌市立病院に赴任しました。6年目の医者というのは基本的に何でもこなせますが、例外ということを知らないため危険な存在でもあります。そんな危険な医者が産婦人科医長として半年ばかり留萌で診療しました。
入局して1年目でターミナル・ケアをマスターしたつもりだった私は、子宮体がん末期の九十近いお年寄りに出会いました。出血のため旭川の病院で診察を受けたところ、がんはかなり進んでおり、歳も歳だし近医で様子をみるしかないと言われたそうです。その後、出血は止まることなく少しずつ続いていましたが、だんだん多くなりご家族も自宅に置いておくのも不安となり、お婆さんを連れて受診しました。さいわい、痛みもなく、いくらか認知もかかっており、お婆さん自身は不安な様子は見せませんでした。ご家族の希望もあり入院管理としました。
今後の治療方針として、看護スタッフに次のように話しました。
「痛み止めはドンドン使う。しかし蘇生はしない」
当時、がんで亡くなりそうな患者さんに対して、点滴で血圧を上げたり、最後は人工呼吸や心臓マッサージをするのが主流でした。要するにご家族に対して、オレ達はここまで頑張っているんだからな、というパフォーマンスです。そのパフォーマンスはしないという宣言にスタッフは動揺しました。師長は、なんてヒドイ医者だ、と言わんばかりに泣き出し、産婆さん風のベテラン助産師は、先生のお考えをうかがいたい、とせまってきました。いくら一人でイキがっていてもダメだと悟りました。
さいわいと言っては何ですが、お婆さんは苦しみませんでした。でも傾眠状態で尿量も減ってきました。よくテレビや映画で余命何か月ですよ、と医者が説明する場面がありますが、婦人科がんに関してはここんところが正直言って分からない。ただし、おしっこが出なくなったら2週間ももちません。入局して1年目の経験で分かっていました。
血圧も下がってきました。ご家族にいよいよ最期だと説明しました。蘇生についてもあらためて確認しました。すると、ご家族の一人が、誰それがまだ来ていないのでそれまで何とかしてくれないか、と言い出しました。しかたなく点滴に昇圧剤やステロイドを入れました。それでも誰それはまだ到着しないので、とうとう人工呼吸や心臓マッサージまでフルに行ってしまいました。意識のないお婆さんにとっては、ただいじくられていただけで気の毒ではありましたが、考えてみたら本人の命は本人だけのものではなく、親しい人、大事な人の命でもあります。そして本来、看取るのは医療者ではなくご家族です。そんな当たり前なことを忘れていました。
みちのくの母のいのちを一目見ん一目見んとぞただにいそげる(斎藤茂吉)
その後、看取りの医学は「死の臨床」、「ターミナル・ケア」、「緩和ケア」と名称を変えながら世の中に浸透していきました。先ほどのお婆さんはご家族や親戚が大勢いて、それらの人に囲まれて亡くなりましたが、核家族の時代、在宅ホスピスの究極、一人ホスピスという死に方も行われるようになりました。人生の最期に関して今後も患者さんやその背景に配慮してきめ細かく検討しなければなりません。(次回に続く)

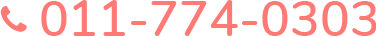




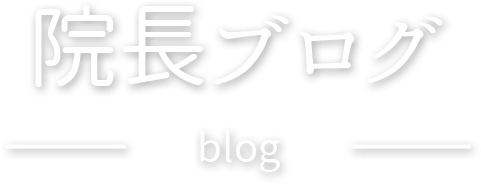




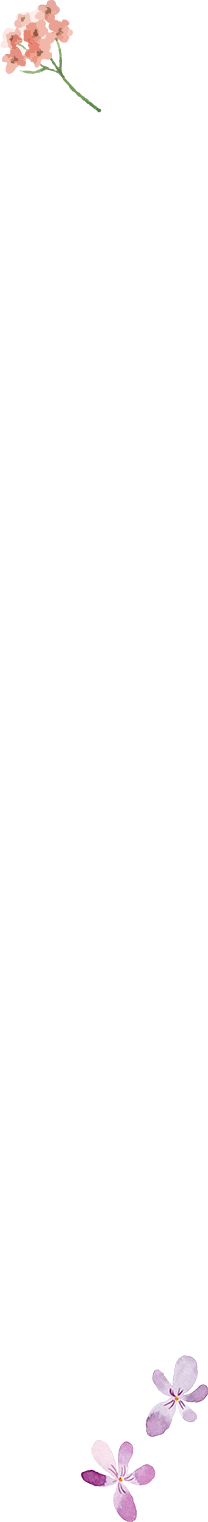
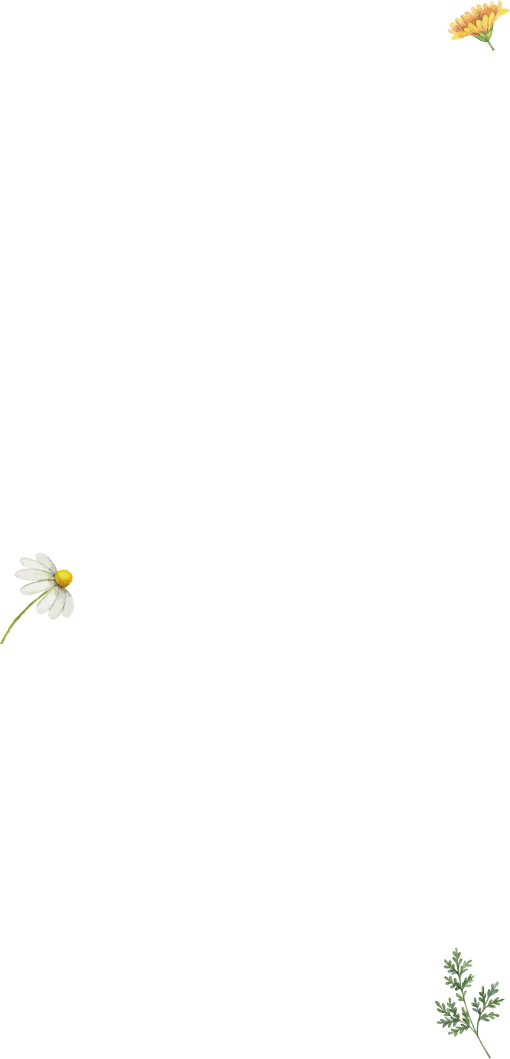
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ