55歳になった女性が言いました。
「更年期が終わってスッキリしました。今思えば更年期まっただ中の50歳のときは地獄でした。でも今度は長女が大変なことになってきました」
娘さんは十代の後半です。排卵期までは元気ですが排卵期を過ぎると、めまい、イライラ、下腹部痛、頭痛といった様々な不快な症状に悩まされるようになりました。そしてきわめつきは生理痛。あまりの痛さに学校を休むこともしょっちゅうです。
要するに年頃の女性は、排卵前、排卵後、月経と、人格が変わるような状態になるのです。また妊娠すると悪阻(つわり)などさらなる人格が現れることがあります。これについては昔から多くの治療者を悩まさせてきました。1800年前に書かれた『金匱要略』という漢方のテキストには産婦人科について多くの記載があります。一方、ヨーロッパではローマ帝国が絶頂期をむかえていましたが、外科治療にはたけていましたが内科関係は弱く、『古代ローマ旅行ガイド』(ちくま学芸文庫)には、「とにかく病気になるな!」とあまり参考にならないような忠告が書かれています。
では『金匱要略』の処方で解決したかというと、そうはいかず現在一般に多用されている処方は11~12世紀の『和剤局方』の加味逍遥散です。逍遥とはお散歩のことで、症状があちこち定まらないことを指しています。それでもダメならと幕末の名医である浅田宗伯は女神散という処方をあみ出しました。
ここでどうして女性のメンタルが変化するのか考えてみましょう。哺乳類としての女性は男性よりも妊娠・分娩などのリスクをかかえています。排卵前は配偶者をもとめて(無意識ですよ)活動が活発になります。排卵後は妊娠の可能性があるため活動は鈍ります。メンタルも落ち込むことがあります。妊娠すれば悪阻などでさらに落ち込み、自殺する例もあります。2016年に東京都が23区での過去10年間の妊産婦の死亡原因を調査したところ、妊娠初期の自殺がトップと判明して、日本中に衝撃が走りました。
ただちに周産期メンタルヘルス学会の重要性が認識され、学会では妊娠初期のうつ状態の薬としてSSRIやSNRIを奨励しました。奨励したのは精神科の医師で、「つわり」という現実を把握していませんでした。SSRIもSNRIも副作用として吐き気があり、悪阻の女性にとって飲めたものではありません。もちろん産後のうつも忘れてはいけません。
何とか妊娠初期から妊娠中期になると、多くの女性は充実感を覚えるようになります。
妊娠後期になると心身ともに再び負担がかかるようになります。そしてお産。簡単にお産と言いますが、なかなかつらいものです。最近、東京都では無痛分娩の費用を給付をすると宣言しました。当院でも無痛分娩を希望する産婦さんにはできるだけ対応しています。無痛分娩の産婦さんを見ているとニコニコしていて、ふつうの分娩は今さらのように気の毒に見えてきました。お産に耐えろというのは男の身勝手な言い分でした。
生理痛は子宮内の血液を排出するために生じる痛みで、お産のミニチュア番です。痛み止めに加えて子宮の急激な収縮をおさえる薬を処方することでかなり改善します。
女性は次世代に命をつなぐためにこのような試練を受けています。もちろんほとんどの女性は何とかやり過ごしていますが、心身ともに負担となっている女性には手をさしのべるべきです。当院の宣伝みたいですが、これは当院の得意分野です。
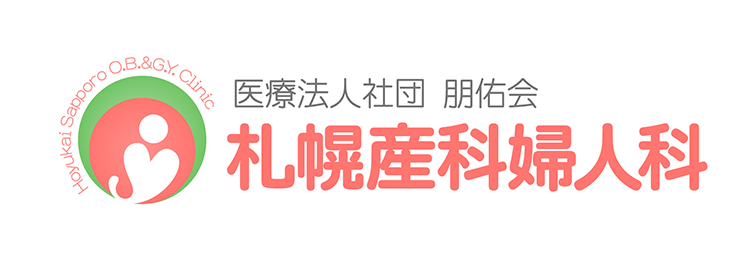
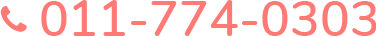









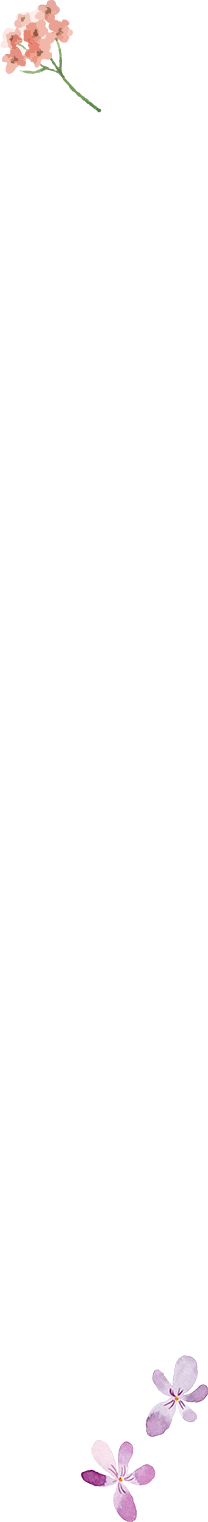
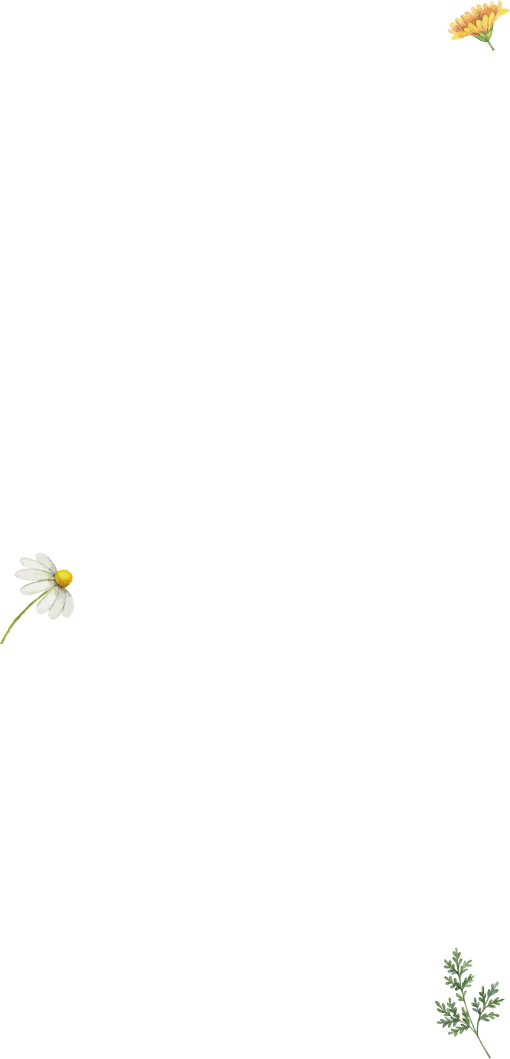
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1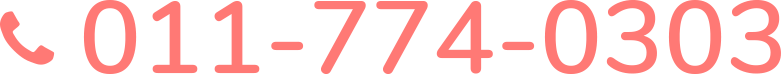
 トップページ
トップページ