産科をめざして医師になった私ですが、大学病院で待っていたのは末期がんの患者さんたちでした。当時は病名の告知もなく、患者さんはただ何となく死を悟っていくというのが現状でした。状態が悪化した患者さんを専用に使っている個室がありました。そのことは患者さんたちにも知れわたっていたようで、ある患者さんはその部屋に収容されてから一言も口をきかなくなりました。まことにもって気の毒なことでした。
絨毛がんの治療を受けていた若い患者さんがいました。元ナースで若い医師をからかうのを楽しみにしていました。今の日本では絨毛がんで亡くなる患者さんはほとんどいませんが、当時は絨毛がんは婦人科がんのなかでももっとも進行が早く、予後不良とされていました。帰宅する前に病室を訪れたとき、その患者さんは言いました。
「どうせ先生たちは患者を死なせて腕を上げていくんでしょ」
予期せぬ質問にビクッときました。生半可な答えでは許してくれそうもありません。
「そのとおり。まず、貴女に死んでもらおうかな」
お互いに笑って何とか部屋を出たものの廊下を歩いていて涙がドッとわき出てきました。新米の私にとっては大きな衝撃でしたが、さいわいにも患者さんは完治しました。
医療は人を生かすのが目的とされてますが、死に瀕した患者さんのお世話をするというのはそれ以上に大切なのではないかと思いました。人は必ず死にます。そして終わり良ければすべて良しです。人生の終わりを充実するようにサポートするのは非常にやりがいのあることだとつくづく思いました。
”がん”という言葉を患者さんの前で口にするのもタブーでした。先輩医師が子宮がんの初期で、子宮摘出だけですんだ患者さんの退院の説明に同席したときのことでした。説明を受けた患者さんは何か納得できないよう表情を浮かべたので、生意気にも私は、「○○さん、実はがんの初期だったんですけど全部取り切れたからもう心配はありませんよ」とつけ加えました。患者さんは明るい表情になってナースステーションから出て行きましたが、先輩の顔は丸つぶれです。本当は気の弱い先輩は私の目を少しそらせて、「佐野よ、患者の前で”がん”という言葉は絶対に言ってはいかんのだぞ!」とドスをきかせた声で言いました。
ある夜、学会の準備をしていたとき、三人の患者さんが廊下を歩いていました。当時、研究室と病室は同じフロアにありました。一人は先ほどの絨毛がんの患者さん、その他、子宮がん、卵巣がんとタチの悪い病気の人たちでした。よせば良いのに、「お茶でも飲みませんか?」と声をかけてしまいました。その部屋は郷久先生の部屋でもあり、勉強家の先生は第二の図書室と言われるほど本を集めていました。ソファーに座った患者さんたちはジッと本棚を見て、読んでも良いかと訊くので、しかたなくOKと言うと、絨毛がんの患者さんは絨毛がんの本を、子宮がんの患者さんは子宮がんの本、卵巣がんの患者さんは卵巣がんの本をたちまち見つけ出し、真剣な眼差しで読み始めました。
いくら病名を隠したってこのとおりです。かえって、どうせ医者は本当のことを言ってはくれない、と信頼関係がくずれるばかりだと思いました。でも、安易に告知するのも危険です。患者さんから希望を取り去ることになるからです。患者さんを中心として、そのご家族、そして医療者がチームを組む必要があります。(次回に続く)
第229回 忙酔敬語 看取り

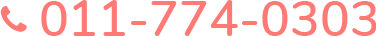




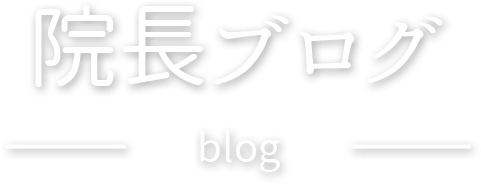




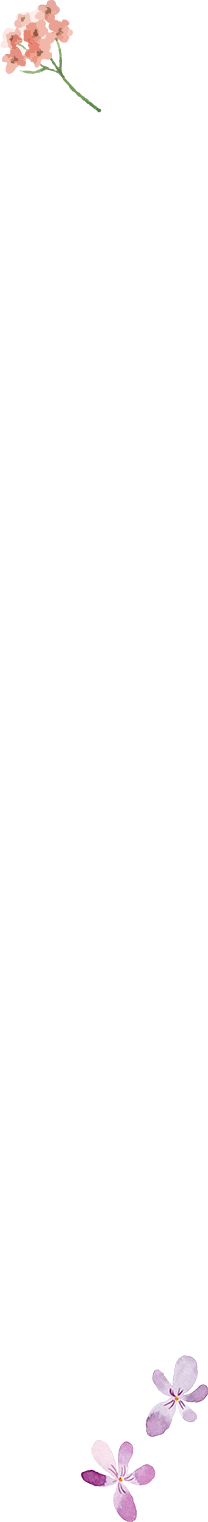
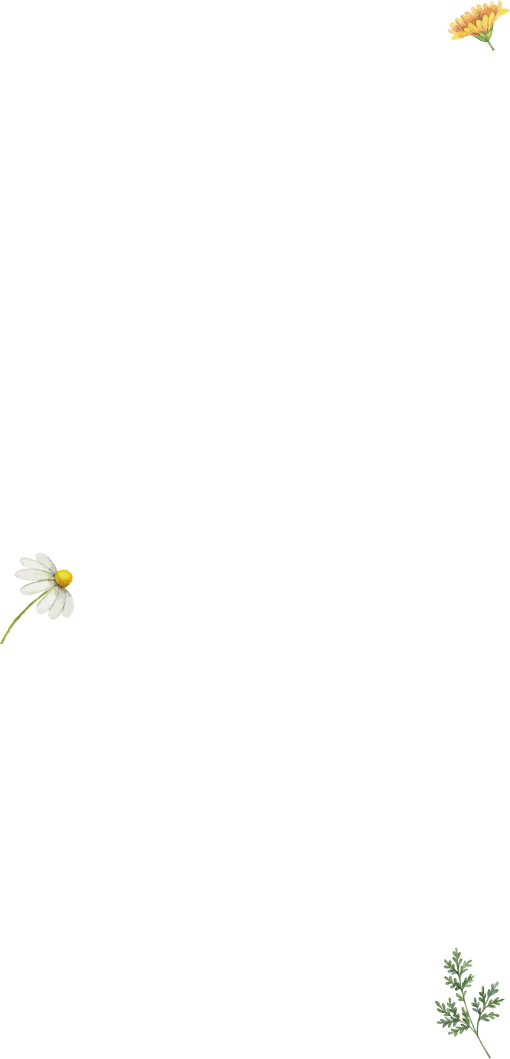
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ