医学生のとき入学してから5年生になるまで一貫して精神科医になりたいと思っていました。人間の本質は精神にあり、その精神をあつかう精神科は診療科のトップと考えていたからです。今はそんなこと思っていませんけど‥‥‥。
ところが6年目になって実習で各科を回ってみて、一般医として外科的な処置も身につけなければいけないなと考えるようになりました。その頃は総合診療科はまだありませんでしたが、無医村地帯にでも働ける医師になりたいなと思うようになっていました。
産婦人科は、更年期障害のような微妙な疾患もありますが、一応外科系の診療科です。とくに産科は人類の存続に不可欠です。講義はつまらなく全く興味はわかず、ノートもたった6ページしかとりませんでしたが、実習で元気なお母さんや赤ちゃんを見て、やりがいがありそうだなと感じました。
産婦人科は明るい産科ばかりではありません。婦人科ではがん患者さんと向き合わなければなりません。婦人科は辛気くさくてゴメンだなと思いながらも、とりあえず札幌医大の産婦人科に入局しました。当時、産科と婦人科は1年ごとのローテーションでした。医局長に「産科をやりたい」と言ったのに全く無視されて婦人科に回されました。
そこで待っていたのは、がんの患者さんたちでした。当時の婦人科がんの末期は悲惨でした。患者さんは、出血や臭気のあるおりものに悩まされる上に、がん性疼痛で苦しんでいました。婦人科がんは直接命にかかわるような部位ではないため、それこそジワリジワリと進行し、真綿で首を絞めるように苛みます。腸にまでがんが進行した患者さんを外科の先生に診てもらったとき、「産婦人科の患者さんはミゼラブルですね」と言った言葉はいまだに忘れられません。
当時、緩和医療という概念はありませんでした。痛みを訴える患者さんにはそのつど日中は主治医が、夜間は当直医がオピアトやオピスコといった麻薬の注射液を金庫から取り出して看護師さんに渡していました。麻薬は依存性があるので最小限に使用しなければいけないというのが常識としてまかり通っていました。あまりにも頻回に痛みを訴える患者さんには偽薬として生理的食塩水を注射することもありました。患者さんはそれでいっときガマンします。医療者はそれが効いたと判断する。今思えばひどいことをしたものです。胸が痛みます。
入局して半年もしないうちに術後やがんの末期の患者さんについては、ほとんど私に任せられるようになりました。そこでほとんど食事を摂れずに痛みで苦しんでいる患者さんに対して、点滴内にオピスコを前もって入れることにしました。それでもつらそうにしていれば、向精神薬のコントミンの注射液を加えました。持続的に静脈麻酔をしているようなものです。
看護師さんからは「先生、そんなことをして良いんですか?」的な目で見られましたが、上の先生は文句も言わずに任せてくれたので続行しました。
当時、産科の指導者だった郷久先生も、「僕ががんになったら、とにかく痛みを何とかしてくれれば良いな」と言ってくれました。そして貸してくれた本が河野正臣著『死の臨床』。私が日々疑問に思っていることがすべて書かれていました。時代はまさにターミナルケアの幕開けでした。(次回に続く)
第228回 忙酔敬語 続・痛み

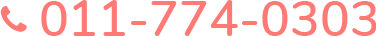




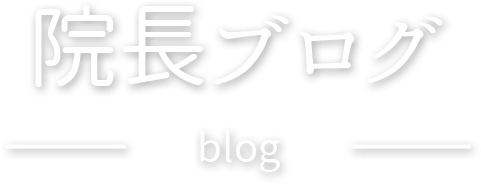




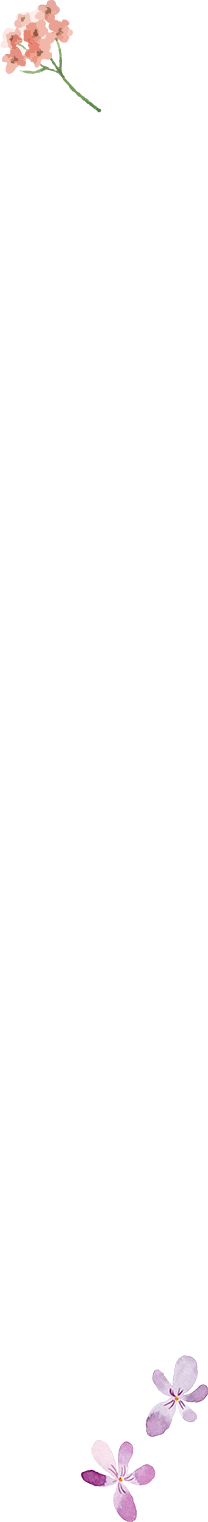
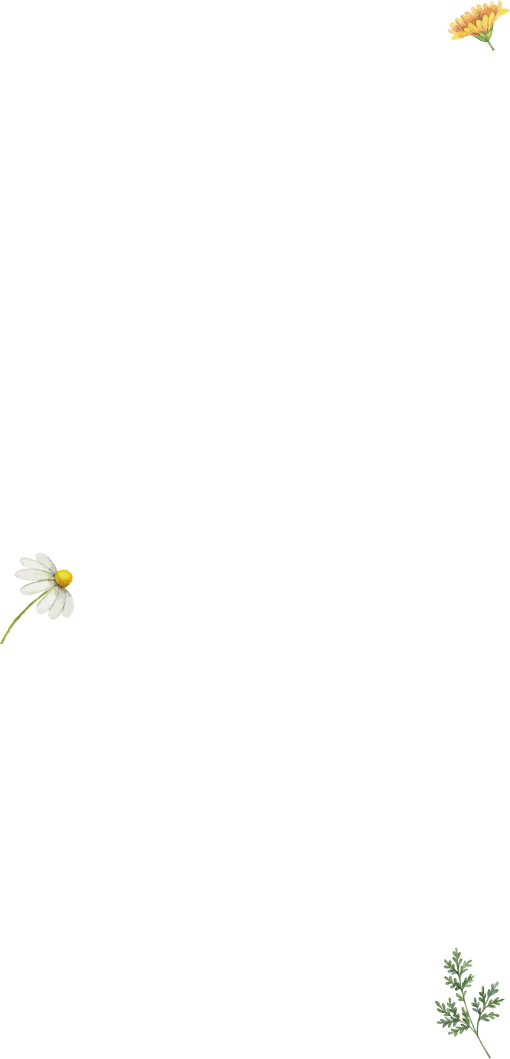
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ