産後の2週間健診や1か月健診のとき、経産婦さんの場合、私はかならず「上のお子さんの様子はどうですか?」と訊くことにしています。
生まれたばかりの赤ちゃんやお母さんの心の平和は家族全体でなり立っています。とくに上の子の存在は重要です。4歳以上だと赤ちゃん返りも微妙ですが、2歳くらいだと赤ちゃんの存在は、自分の人生の妨げになるんじゃないかという本能がはたらきます。当然のことです。それを「もう、お兄ちゃんなんだから我慢しなさい」などと言っては大変なことになります。最近は周知されてきたのか禁句として認識されているようです。
2歳のお兄ちゃんが言ったそうです。「お前なんかママのお腹にもどってしまえ!」
お兄ちゃんには気の毒ですが思わず笑ってしまいました。今年、小学一年生になった子は、早生まれの赤ちゃんが生まれる前に言いました。「もし、みんなが赤ちゃんばかり可愛がれば、撲、家出するからね」
この話をしたら、皆さん、「まあ、可愛い!」と笑いました。
実際に赤ちゃんが生まれた後は、お兄ちゃんは赤ちゃんを溺愛し、「ほら、僕が抱っこしたら泣きやんだよ」とマウントを取りました。
このように自分の気持ちを率直に表現できる子はあつかいやすく、その後、健康な人生を歩むことになります。
自分の心を抑えて我慢する子は要注意です。我慢しているかどうかはよく見れば分かります。私の孫娘が2歳過ぎのとき、その弟が生まれました。文句は言いませんでしたが、ジッと唇の皮をむしっていたので、複雑な心境であることが見て取れました。そこで私は、チューリップの咲く頃でもあったので、ヒマさえあれば一緒にお散歩しました。4年前は白いチューリップはレアな存在だったので、白いチューリップをもとめてさまよいました。こうなると私の趣味が加わり、どちらが大人だか子供だか分からなくなります。しかし、遊ぶときは両者ともに子供の心になって夢中になることが大事だと心理学で証明されています。そのため、私は孫娘の一番のお気に入りとなりました。
3人姉妹で3年連続の年子の長女がいました。気立ての良い明るい子でしたが、高校生になったとき、「もう、みんなキライだ!」と家を飛び出しました。両親はあんなにはつらつと元気だった娘の急変に驚きました。娘さんは幼少期から妹たちのお世話をする良い子でした。しかし、本当は自分の心を殺していました。その証拠に小学生になる前の記憶がありません。すべて押さえていたのです。家族全員が以前のように仲良くなるまでに半年もかかりました。その後は、もともと気立てのよい子なので、それまで以上に仲良し家族となりました。
私も妻も長男と長女で、一番上の子の心の葛藤を経験してきたので、二人の娘がケンカしてもどちらに加担することはなかったので、ケンカはすぐおさまり、その後、親友以上に仲良く育ちました。
何も強制しなければ子供はすくすく育ちます。しかし子供の成長を妨げる物が現れました。スマホやタブレットです。表情や声、匂いといった人間の温もりのない情報が脳に侵入して来るので、その後、人とのかかわりに悪影響をおよぼします。発明者の一人であるスティーブ・ジョブズはいち早くその危険性に気づき、自分の子には禁止としました。
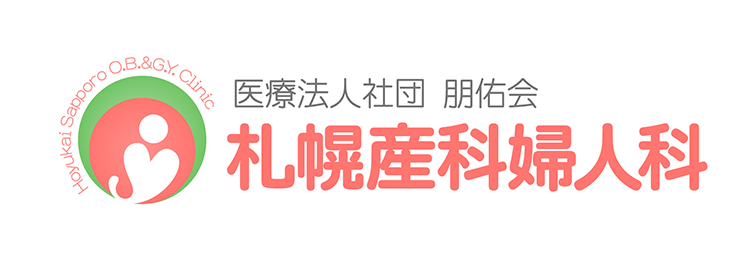
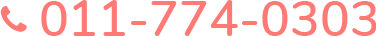









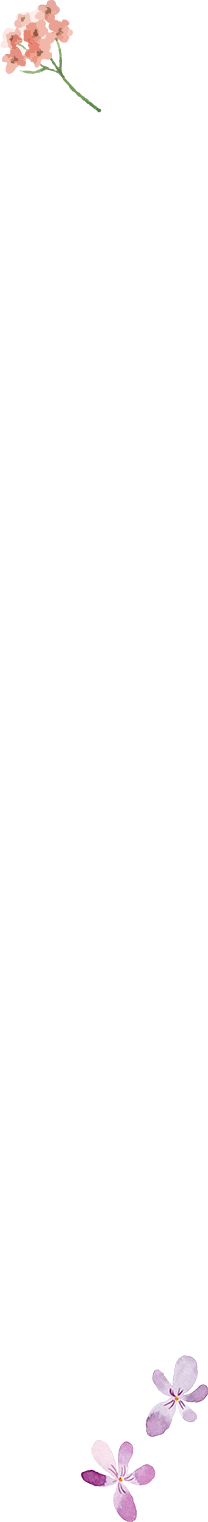
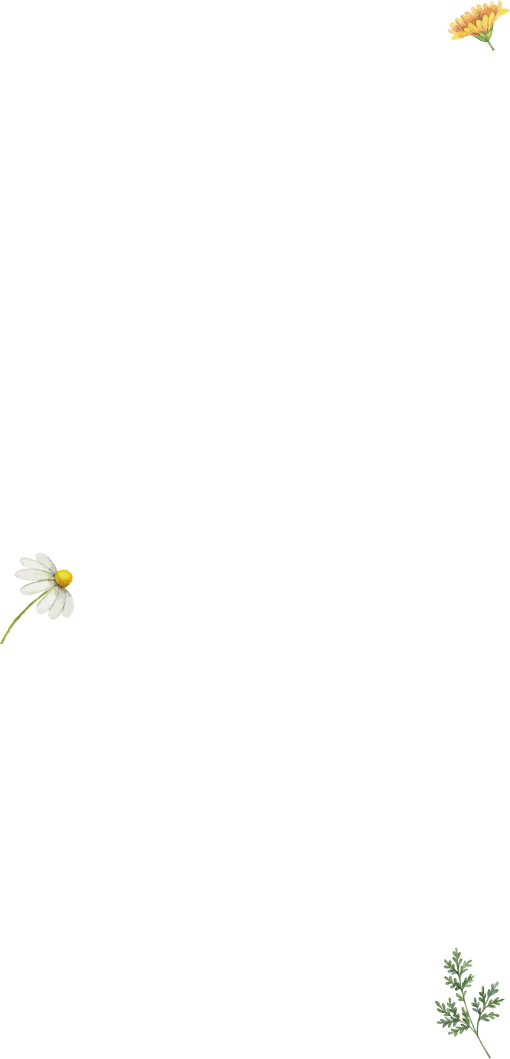
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1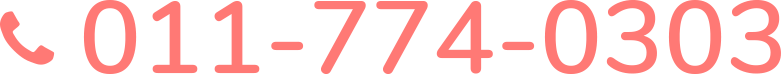
 トップページ
トップページ