戦後80年がたちました。私の嫌いな言葉、「戦争を知らない世代が増えてきた」。平和が続けば当然、戦争を知らない人々が多くなります。そうすると戦争の恐ろしさが忘れ去られると言うのです。再戦に対する恐れですが、当たり前すぎてバカバカしくなります。
私の父は中国北部(満洲)で終戦をむかえ、ソ連軍の捕虜となりシベリアに抑留されました。4年間、よくぞ生きぬきました。父はエリート会社員でしたが、田舎医者の三男で、生きぬくための基本的なノウハウをふつうの人よりも知っていました。捕虜たちを苦しめたのは餓えです。そのため地面に落ちている食べてはイケナイ物まで拾って口にする者まで現れました。父はガリガリにやせ細りましたが我満をつらぬいて生きのびました。父の兄である長男は南方に軍医として徴集されました。一応、生きて帰還しましたが肺結核になり肺の一部を切除されました。父と一番の仲良しだった次男は戦死しました。
このようなことを子供の頃から聞かされてきた私は、戦争の一部を知る世代です。では何も知らない若い世代には戦争の悲惨さをどう理解してもらえばいいのでしょうか?
単なるお話しでは主観が入ります。一応、理系の私は統計による確かな数字を知ってもらうのが一番だと気づきました。それが人口動態の推移です。
大戦で230万人の日本兵が犠牲になりました。民間人も含めると300万人以上の男性が死亡しました。人口動態の図は、多産のため赤ちゃんの人口が多く、高齢になるにつれて減少します。そのため通常はピラミッド型になり、今でも人口ピラミッドと言われています。しかし、少子高齢化によりピラミッドは紡錘形となり、出生数の低下にともない高齢者の方が多くなり、今の日本はツボ型となってしまいました。
話がそれました。大戦で死亡した男性の実態は、人口ピラミッドに現れました。すなわち、戦争に参加した世代の男性の部分が少なくくびれていたのです。父の世代の人口の凹みを見るたびに、戦争って残酷だなあ、と実感しました。この凹みは当然ですが、時代が進むと同時に上方に移動しました。父が生きていれば、すでに100歳以上、その凹みは消失しました。
今現在の人口ピラミッドを見れば、どこが悲惨なのか分かりませんが、ネットで検索して過去のピラミッドを見れば一目瞭然です。人の体験談を読むよりも、統計の数字の方が信頼できます。別に語り継ぐのが無意味というワケではありませんよ。ただ自分の目で確かめて欲しいのです。
ここであらためて人口ピラミッドの推移を調べると、団塊の世代の人口爆発、少子高齢化、将来の状況ばかり強調されているようです。戦役の時代の男性の凹みなんてその気にならなければ分からなくなりつつあります。
私の小中学校の社会科の教科書では、別に解説がなくても明らかに凹みの推移に気づかされました。だんだん私も戦争を知らない世代に巻きこまれつつあるような気がしてきました。アブナイアブナイ。
こうなるとドラマや映画に頼るしかありません。現在の朝ドラ『あんぱん』、BS再放送の『チョッちゃん』、昨年ブレイクした『虎に翼』、朝ドラ再々再々放送の『カーネーション』・・・・。戦争の悲惨さがヒシヒシと伝わります。ただし、最近の若い世代はテレビも見なくなりました。体をはって戦おうとする気配がないのが救いです。
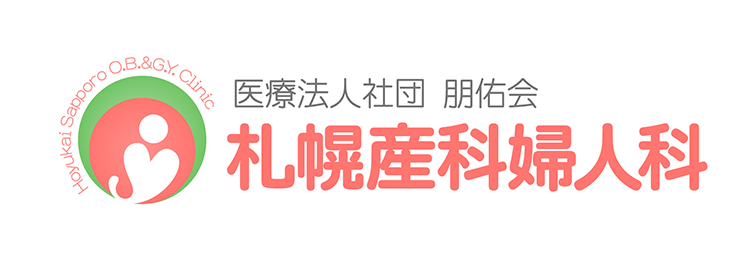
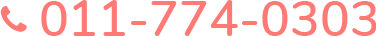









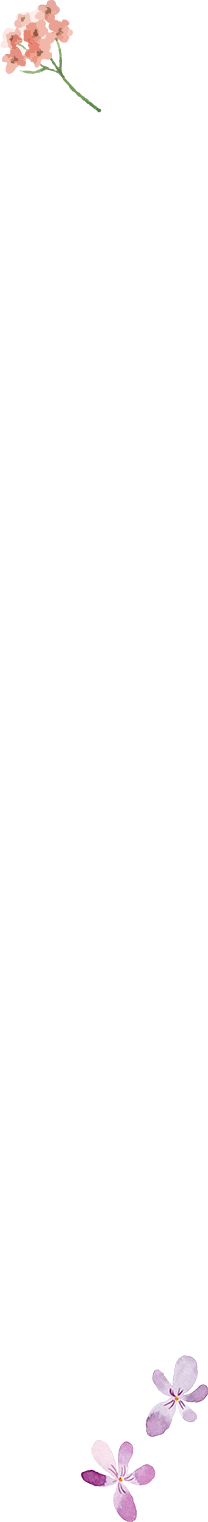
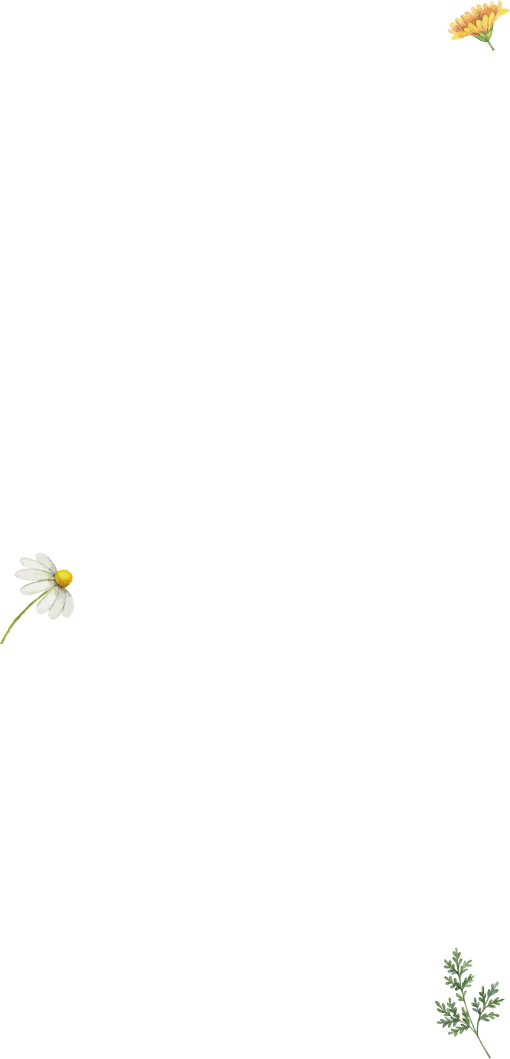
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1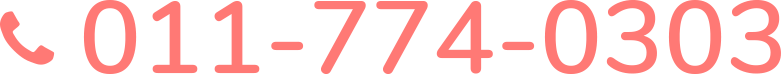
 トップページ
トップページ