夏至は過ぎましたが日照時間はまだ長いままです。朝5時の早朝出勤は明るくて気分が高まります。車はほとんどなく、あたりはすべてオレのものと言ってもよく、咲いている草花や鳥の声などをネタに俳句を5つ6つ詠みながら歩いています。締めの句はお友だちの大きな柳の木です。お友だちは葉がびっしりと繁りまさに最盛期です。締めの句を詠んでもさらに新しい出会いがあればつけ加えます。そんなときは何だか得した気分になります。医局に着いたら忘れないうちにパソコンに書きとめます。そんなことをして何になるの?と思われるかもしれませんが、私の数少ない趣味の中でもトップの位置をしめています。心身ともに癒やされるしタダです。さらに言えば自分が生かされている、ということに気づきます。そしてつくづくありがたいな、と感謝の念が生じます。
日本の心身医学を確立した九州大学心療内科初代教授の池見酉次郎先生は、心身医学だけではダメ、「心」「身」に「社会」「倫理」も加味して全人的な医療をめざしなさい、と言われていました。そして、カウンセリングのゴールは「生かされている自分に気づき、それに対して感謝の念を抱くことです」と締めくくっておられました。
私は、それに「生態」をつけ加えるべきと考えています。池見先生は精神分析を学ばれ、宗教、とくに仏教に造詣が深い先生でした。理系、文系に分類すると文系に重きを置いていた感があります。カリスマ性があり、愛弟子の郷久名誉理事長のご縁で直接お目にかかることができたのは私の人生の宝です。しかし、科学という理系的な観点から見ると、池見先生以上に発展する余地は少なく、実際、心身医学会は尻すぼみの状態です。
「心」「身」につけ加えられた「社会」「倫理」は観念的で、理系の科学として理解するのには限界があります。生態学は人間を取りまく環境について研究する学問です。そこから人間全体を観察することで、心身医学においても科学的な研究が深まるはずです。
現在の生態に思いをはせるのにはどうしても生命の進化について知らなければなりません。私は令和になる前からそのことに気づき、昨年、ある学会の一般講演で発表しました。講演時間はたったの7分です。講演した内容はその学会誌に投稿することになっていますが、4、5ページではとても書ききれません。10ページほどのパンフレットになってしまいました。そこから「生かされている」ことに気づいて欲しいと願いました。
パンフレットのネタは専門書ではなく多数の一般書です。それに日ごろ自分の考えていることをつけ加えて書いたので科学論文とは言えません。寄稿文として投稿しました。査読してくださった先生は「面白かった、続きが読みたいです」と言ってくれたので、調子にのって19ページの元ネタ集を書きました。その元ネタというのは、今まで書いてきたブログから拾った文章です。どう見ても科学論文とは言えません。
学会誌にはいまだに掲載されていませんが、私の診療のスタンスとなっている内容なので、二つの看護学校に講義の資料として使いました。一つめの学校は講義を引き受ける際、校長先生に「何を話していいですか?」と念をおしたら快諾していただいたので問題ありませんでした。しかしながらもう一校からは事務方の理事が訪ねて来て、「授業方針にそっていない、と社会人の学生からクレームが来たので今後このような講義は謹んでください」的なお願いを受けました。私も大人ですから笑って「分かりました」と応対しました。
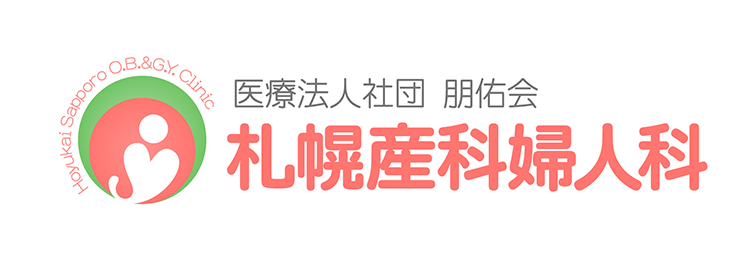
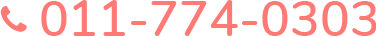









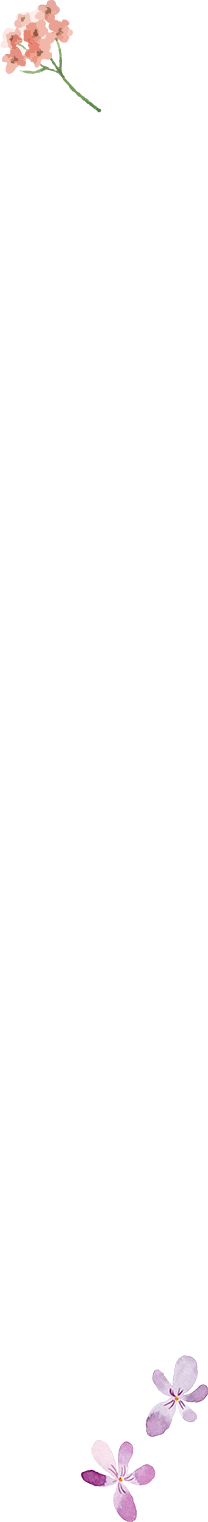
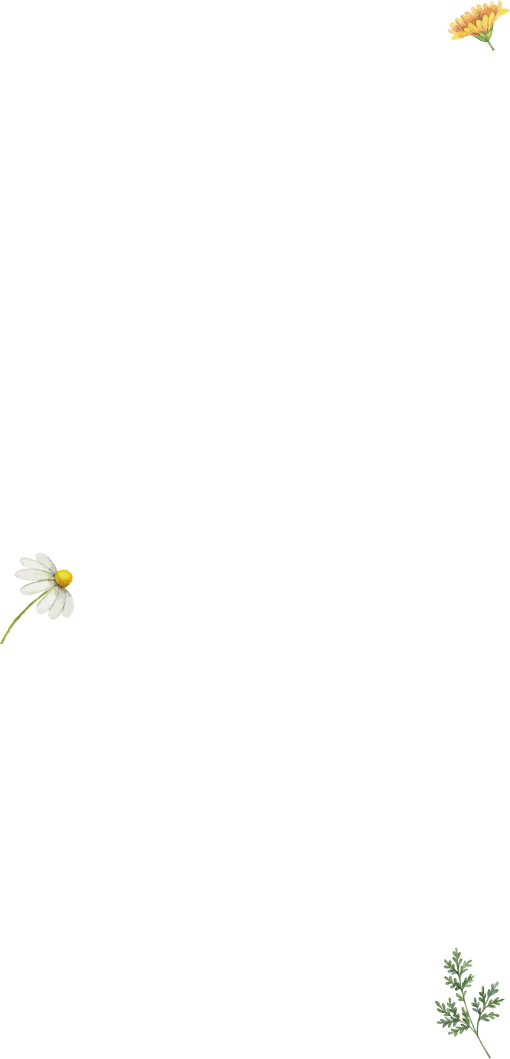
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1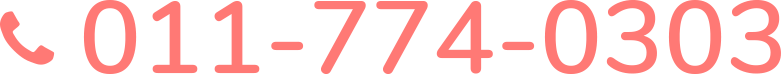
 トップページ
トップページ