私の診療の基盤は心身医学です。師匠の郷久鉞二先生が昨年、長年の成果をまとめて『新・女性の心身医学』を出版しました。私も最終章の東洋医学を執筆しました。郷久先生の血と涙の結晶ですが、私としてはちょっと物足りない思いが残りました。
心身医学というと特殊な分野と思われがちで、実際に心身医学会の会員数も減少しています。しかし心と身体を同時にあつかうということは医療に従事する者の基本です。日常生活で人と交流するときは、誰でもそれなりに気を使いますよね。それ、それです。その気の使い方を研究するのが心身医学なのです。
九州大学心療内科初代教授の池見酉次郎先生は、「心」「身」だけではダメ、「社会」「倫理」も加えて人間全体を診るべきだと主張されていました。私はそれに「生態」もつけ加えて、人の住む環境問題を考えるべきだと気づき、それで物足りないと思ったのです。
家庭農園をやっているとその土地や気候に合う植物の移り変わりに気づかされます。温暖化のため昨年はジャガイモよりもサツマイモが美味しく収穫できました。人も生活環境に無理があれば心身ともに健康を害します。いくら心身症的な治療をしても限界があります。ですから私は疲れはてた患者さんに言います。
「その会社は貴女の命をささげる価値がありますか?」
生態学を学ぶには現在の生態に至った進化についても知らなければなりません。私は令和になる前からいろいろ調べて、昨年、その成果をある学会で発表して、さらに10ページほどのパンフレットにまとめました。
動物の起源は5億年以上も前のカンブリア紀の海中で始まりました。たった6000万年の間に現在の動物たちの祖先が出そろいました(カンブリア爆発)。動物が陸上に上がるのは4億年前に植物によって地上の用意が整ってから1億年後のことでした。私の知識はそのあたりが曖昧でした。その穴を埋めてくれたのが藤井一至先生の『土と生命の46億年史』です。藤井先生いわく、自分の主な研究道具はスコップで、これを持って世界中の土を掘って研究しているとのことです。
〈自分の目で見なければ納得できない私は、カナダ・アルバータ州の地層を訪ねたことがあるが、迫力不足で正直がっかりした。恐竜絶滅の原因とされる隕石衝突を記録する地層はほんの数センチメートルの厚さしかない。数メートルの火山灰が一度に堆積するするのを知っている日本人からすると、隕石だけで恐竜が絶滅したとは考えにくい。隕石以外にも恐竜絶滅との関わりを疑わせる物質には身近な物が多い。ジュラ山脈の近くの森の土を掘らせてもらうと、私のスコップはすぐに分厚い石灰岩にぶつかった。アンモナイトを含む石灰岩は、ジュラ紀から白亜紀にかけて存在した広大な亜熱帯の浅い海でサンゴが化石化したものだ。この時代、サンゴだけでなく大繁殖した植物プランクトンが酸欠で大量死して化石化した遺体が中東の石油となった。この結果、大気中の二酸化炭素が大量に地下に固定された。同じ白亜紀に陸地で増加したのが被子植物とキノコだ。被子植物は光合成の能力が高い。その結果として大気中の二酸化炭素が消費された。陸と海との両方で二酸化炭素は消費され地球は寒冷化した。巨大化した恐竜は温暖環境に適応したスタイルであり、寒冷化に対応できずに絶滅した。〉
スコップ一本でここまで推理するなんてスゴイですね。
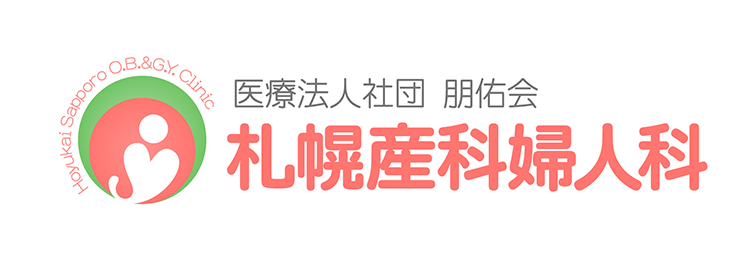
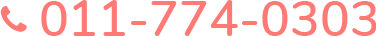









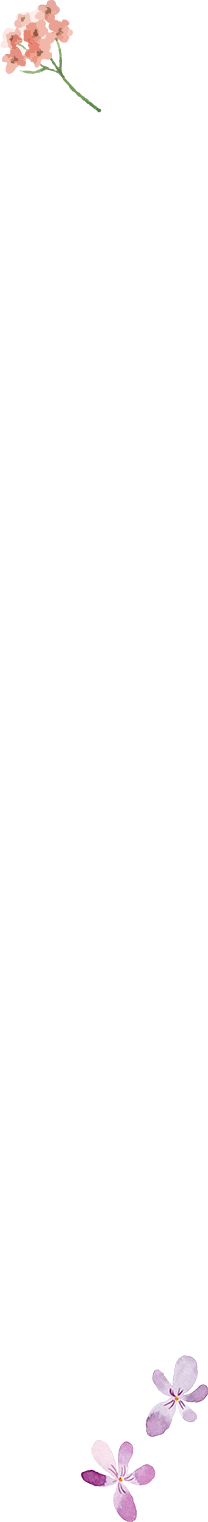
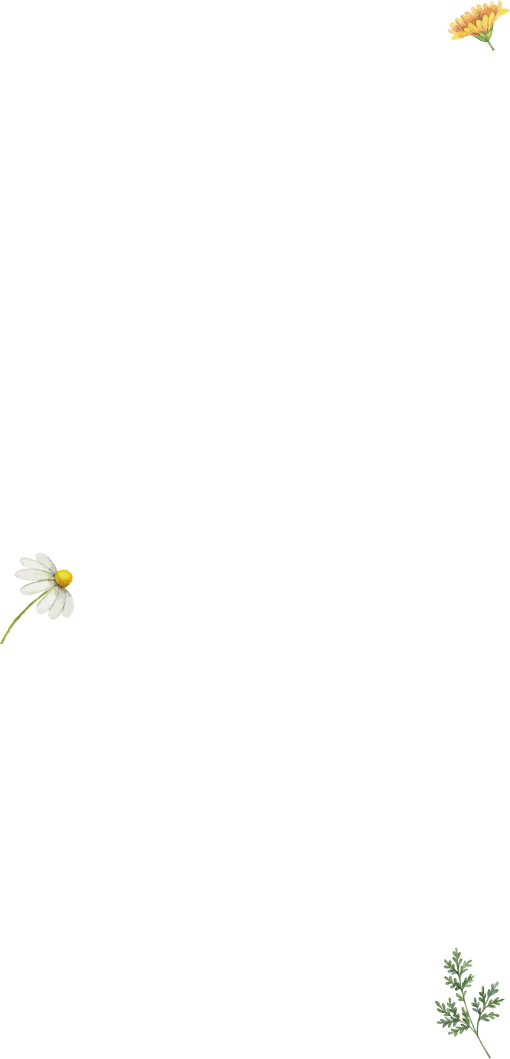
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1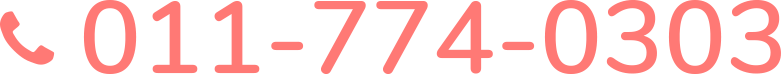
 トップページ
トップページ