30歳代の女性が、ある産婦人科クリニックで子宮内膜症と診断され、ジエナゲストによる治療をすすめられました。そして確認のために当院を受診しました。いわゆるセカンドオピニョンです。そこで思い出したのが高知医大でのことでした。
四国、とくに高知県は人口あたりの医師の数が全国の2倍以上です。私は大学院生のとき、高知医大の相良祐輔先生にカテコーラミンを分析する実験方法(液体液体クロマトグラフィー)を習いに行きました。そのとき、相良先生がため息をつきながら言いました。
「ここはやりにくいところだぞ。患者は医者のことをなかなか信用しなく、尊敬の念もない。医者のことは、お医者お医者と言ってバカにしている。お医者さんとか、ましてや先生なんて間違っても言わない。初診で納得しても必ず別の診療所でウラを取ってからでないと治療は受けない。大学病院に来ても、別の病院で確認してから治療を受けないと、親類縁者から、そんなに簡単に信用していいのか!と注意される。だからここは医者の数が全国の3倍も必要なんだ」
ようするに高知県は日本におけるセカンドオピニオン発症の地とも言えます。高知(昔は土佐と言われました)はいわゆる辺境の地で、都落ちした人間が集まるところでした。『土佐日記』の紀貫之がそのハシリというか、代表格です。
したがって一流の人間は集まらず、医者もろくなヤツはいないので、自然、医者に対する信用も他県とは一線を引くようになったのでした。
漢方医学の中興の祖といわれる大塚敬節先生も、そういった面では気苦労をされたようです。大塚先生は高知出身なので、若かりし頃は地元で診療されていました。当時、漢方医学は、明治政府の西洋医学優先の方針で、日の目があたらない状態でした。しかしながら、大塚先生は漢方に引かれて独学をしていました。
ある日、小学2年生の女の子が人事不省のため診てもらいたいと親族から依頼されました。何でも半年前に大阪の小学校に通っていて、運動会での事故をきっかけにこんな状態となり、一族のいる高知に引きあげてきたということでした。
大塚先生が診るに、女の子は意識はもうろうとしているが、時々あくびをする。先生は『金匱要略』に、あくびをする女子のことが書かれていたのを思いだして、その治療薬が甘麦大棗湯であることを確認しました。
家族ははなっから大塚先生に治してもらおうなんて期待していない。ただ死んだら死亡診断書を書いて欲しいと言うのでした。漢方を処方すると言ったら時代背景もあり、ややこしいことになる。そこで診療所で煎じ薬を煮出して内容は伏せて女の子に飲ませたところ、みるみるうちに快復して半年後には元気に学校へ通うようになりました。
さて、その初診の患者さんが受診した時間帯は、たまたますいていたので、私はセカンドオピニオンや高知県の土地柄など、調子に乗ってバカ話をしてしまいました。そして前医の治療方針は完璧だとも説明しました。
「どうします? ○○先生のところでジエナゲストと処方してもらいましょうか?」
私は、バカ話で患者さんの信頼を失ってしまったと思い込んでいました。
「いえ、ここで治療してください!」 さいわいなことに私の話はすべらなかったようです。

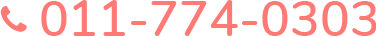




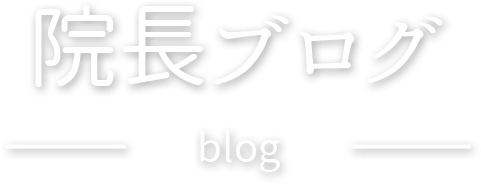




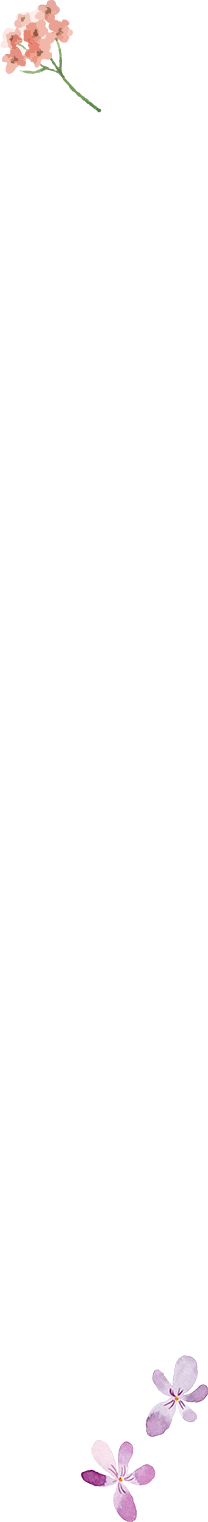
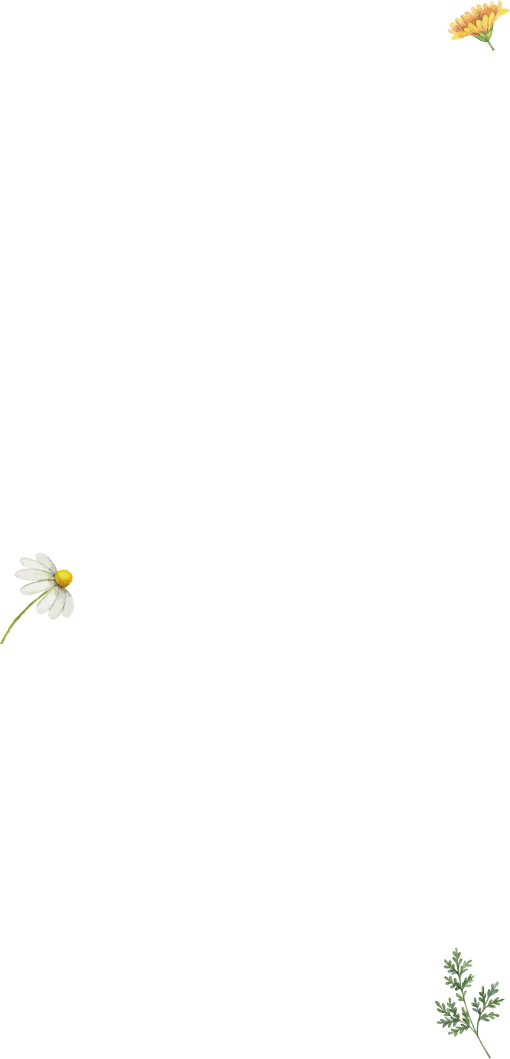
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ