日本医師会雑誌の「主訴から紐解く精神症候学」No.5の題名です。これから紐解けるのは決断力の低下で、うつ状態の兆候ということです。2ページにわたって「うつ」の診断や対応などについて述べられていました。こんなセリフを吐いたからといって必ずしも「うつ病」と決めつけられるワケではありません。疲れはてたら誰だってこんなふうにもなります。さらに深刻になれば「いっそ死んでしまいたい」(希死念慮)の段階まで進むかもしれません。ここまでになれば精神科の先生にお願いすることにもなりますが、だからといって、これでも「うつ病」とまでは診断されません。危険回避の方向を探られます。患者さんの生活環境についての整理整頓がカウンセラーによってなされるはずです。
ここで思い出したのが、脳神経外科医・心療内科医で、頭痛外来クリニックの北見公一先生の心身医学誌の巻頭言に掲載された表題です。『正常を救うのは心身医学だ!』
今まで述べたような患者さんを診てもすぐに「うつ病」と決めつけるな、大事なのはていねいに生活環境を整えることだ。「心」ばかり診ないで「全体」も診なさい。簡単に抗うつ薬を処方される患者を救うのは心身医学をわきまえた医師である、というような内容でした。私は北見先生から心身医学の勉強会などで頭痛の治療をある程度教わってきました。そしてこの巻頭言には感銘を受けました。心身医学は、医師の間でも特殊な領域と思われがちですが、残念なことだと思っています。心身医学会の会員数も減少し、毎年行われている北海道支部例会での演題数は十にもおよびません。昔はワークショップまでやっていたのになあ・・・。郷久名誉理事長はそれにもめげずに昨年、『新・女性の心身医学』を出版しました。心身医学の普及のため、研修に来る学生には一冊ずつ贈呈しています。
心身医学の日本の創設者である九州大学名誉教授の池見酉次郎先生は、生前、「心身医学は心身一如をモットーとする東洋医学に学べ」と言われていました。確かに「わたし、もう死にたいです!」という患者さんに鍼治療をすると、その場は何とかしのぐことはできます。また、漢方薬のなかにはメンタルにも配慮した処方はたくさんあります。
漢方薬も歯車がピタッと合えば、メンタルの不調を訴える患者さんがビックリするほど良くなることがあります。しかし、効いた、効いたと喜んでいてはいけません。なぜ、そのような薬が必要になったかを確認しなければなりません。大阪の泉州統合クリニック院長の中田英之先生は、もともと産婦人科医ですが精神科も標榜しています。3年前に札幌で日本東洋医学会で教育講演をして頂き、私が座長をつとめました。講演内容は養生でした。漢方と鍼治療で名をなしていた先生は、ほとんど漢方は処方していないとのこと。せいぜい胃を整える茯苓飲で何とかなるそうです。胃腸を整えることは心身医学の基本です。2年前から私が頻用している平胃散もそのような薬です。適度な運動と足湯をすすめていました。昔、中田先生が札幌で公演したときは、「漢方を飲む前にまず甘い物はやめてもらいます。とくに果物はダメです」。さすがに本当かな?と思いましたが、実際に桂枝茯苓丸で体調が良くなった若い女性が「最近、またスウィーツが食べられるようになれました」と喜んでいたことで、本能のなせるワザで自然に甘い物を受けつけなかったんだと判明しました。簡単には漢方を処方しない中田先生に大阪弁で「そんなことで儲かりまっか?」と聞いたら、「精神科の指導料で儲かります!」と胸を張りました。関西人らしくヒューマニズムだけでなく抜け目もないのでした。
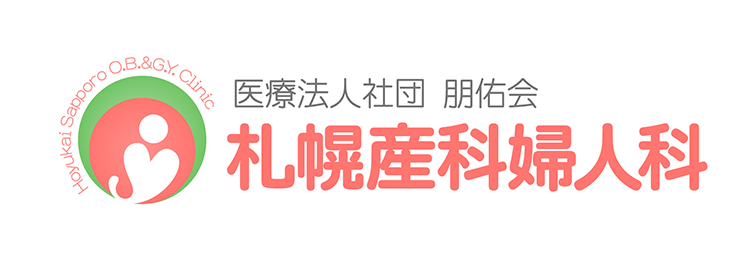
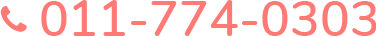









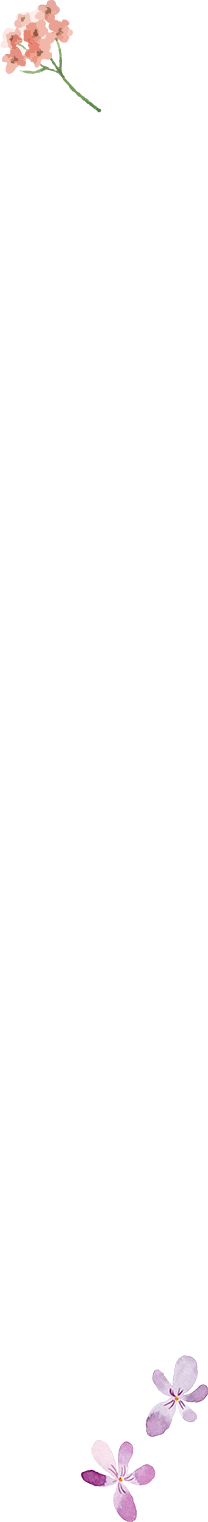
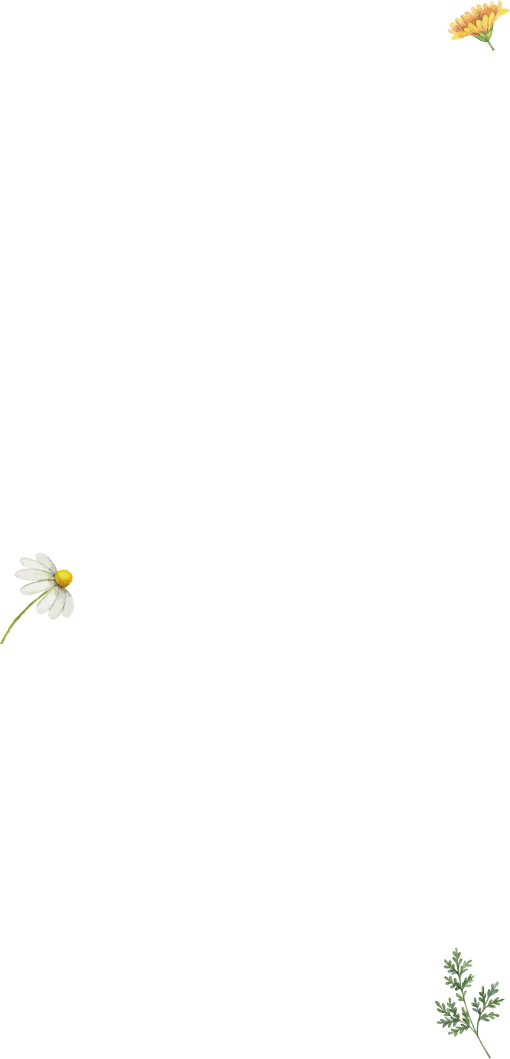
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1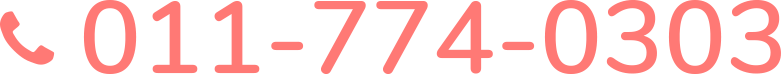
 トップページ
トップページ