子供の頃から神話が好きでした。華やかなギリシャ神話も好きでしたが、どこか不思議な雰囲気のある日本の神話も好きでした。子供の時分はイザナギとイザナミの性交渉による国作りは知りませんでしたが、長ずるにおよんで世界でも類を見ない合理的な知識に基づいた神話だなあ、と感心しました。
イザナギ・イザナミは創造者なのに、イザナミは自分が作った覚えのない冥府の世界に陥り、イザナギも凶変したイザナミに殺されそうになります。高天原を追われたスサノオノミコトはイザナギ・イザナミが作ったという記載のないヤマタノオロチを退治します。
かように『古事記』の神話は矛盾に満ちています。イザナギ・イザナミの性交渉はその後、農業の根本として、村祭りのときの性開放や男根型の道祖神として形を変えて伝わりました。家族計画協会の北村邦夫医師は、イザナギ・イザナミ神話は合理的で日本人が世界に誇るべきものである、と解説していますが、アフリカの民族の中には男性が大地と直接性交渉して豊作を祈る風習もあり、農耕民族では特殊なしきたりではないようです。
さて、それでは『古事記』にはどうしてイザナギ・イザナミ作った覚えのない神様や怪物が登場するのでしょうか? 私は道を歩きながら考えました。そうだ、進化だ!
地球上の生物はすべて1つの遺伝子(DNA)が起源となっています。それが何十億年もかけて進化して多様な生物が登場しては消えていきました。はじめは原始的なバクテリアでした。それとくらべればイザナギ・イザナミの作った神様からとんでもない怪物が登場しても何ら不思議はありません。
話はそれますが、出雲大社にはオオクニヌシノミコトがまつられています。オオクニヌシノミコトは元暴れん坊のスサノオノミコトの試練をのりこえて、めでたくスサノオノミコトの娘をお嫁さんにします。その他、因幡の白ウサギを救ったことで知られています。
また、一寸法師のようなスクナヒコナノミコトと競走して負けました。
こういった逸話の多い神様は、いろいろな神様の合体であることが多く、その後、七福神の大黒天と同一視されるようになりました。大黒天はもともとインドの暴れん坊の神様で、五穀豊穣の神として大黒様(オオクニヌシノミコト)と合体してしまいました。
日本神話だけでなく、多神教の神様はいろいろ合体したり、別の民族の神様になったりします。ギリシャ神話の主神ゼウスはローマ神話ではジュピターとなり、アプロディナはビーナス、ヘルメスはマーキュリー、アルテミスはダイアナなどとなりました。そっくり同じではなく、それぞれ異なったエピソードがあります。私が子供の時分に読んだのはローマ神話だったようです。
私は大らかな多神教が好きですが、一神教も多神教の影響を受けることがあります。本来、一神教であるキリスト教では聖母マリア様が信仰の対象になるはずがありませんが、ローマ世界の影響でマリア崇拝はカトリックの世界で広がっています。それに対してガチンコのプロテスタントは聖書至上主義なのでマリア様は無視です。
仏教も本来はお釈迦樣一筋のはずですが、密教では大日如来を中心に多くの菩薩や、大日如来が姿を変えた不動明王など、仏教美術の対象になっています。
私がお世話になったある先輩は、出生時に洗礼を受けたクリスチャンでした。その先輩に多神教の魅力を語ったところ、素直な先輩は「多神教って良いなあ!」と言いました。
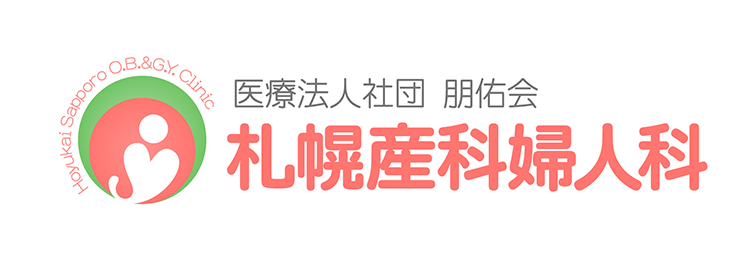
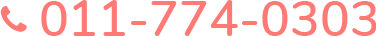









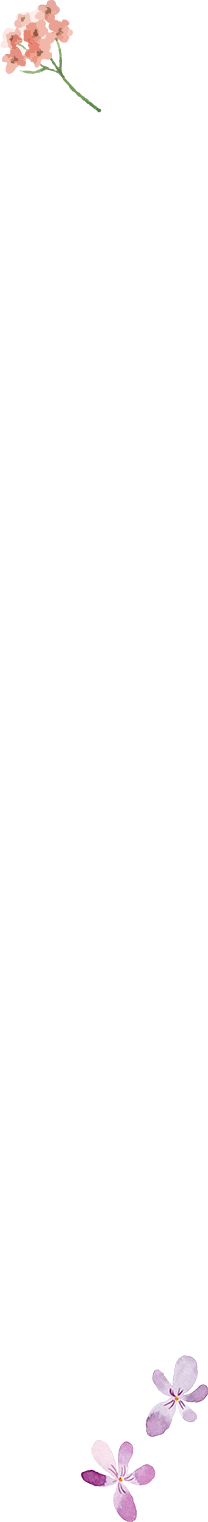
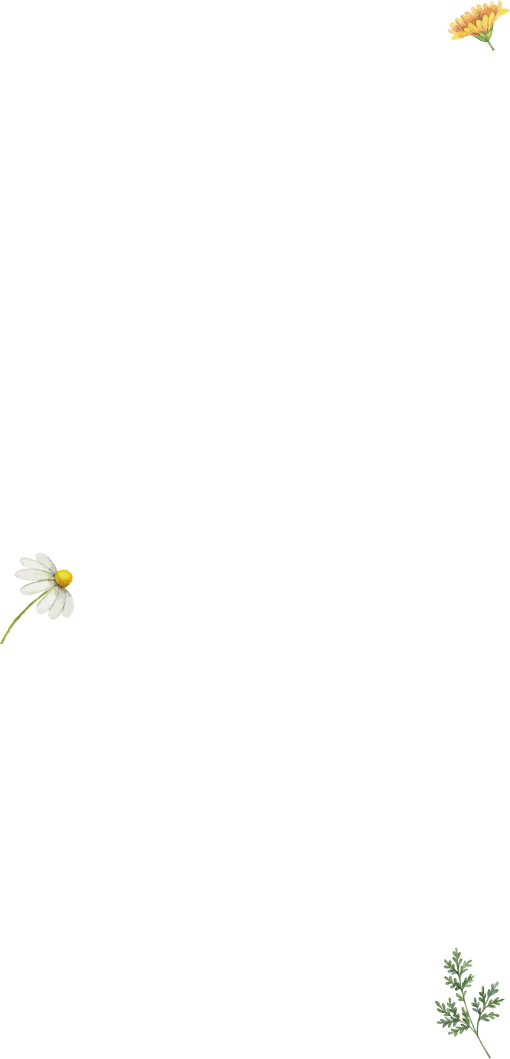
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1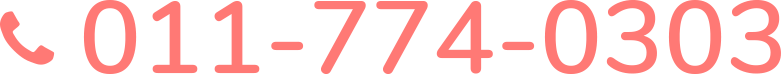
 トップページ
トップページ