私はほとんど小説は読みません。作り物で何だかウソっぽいからです。しかし『青い壺』は別です。ある職人が焼き上げた奇跡的な出来映えの壺をめぐる小話をオムニバス形式で書いた小説です。壺の出来もさることながら、作者の有吉佐和子さんの筆力がそれこそ職人技で、誰が読んでもその面白さに引き込まれます。
単行本も文庫本も有吉さんが亡くなった後、いったんは廃版となったのですが、文春文庫編集部の山口さんの目にとまり、あまりの面白さのため復刊となりました。有吉さんは『華岡清洲の妻』とか『恍惚の人』といった話題作で人気をはくしました。それらとくらべて『青い壺』は話題性がなく忘れ去られました。しかし復刊後はアレヨアレヨという間にロングセラーとなり現在に至っています。
絵画は「何を描いたか」というよりも「どう描いたか」という点で評価されます。文学作品も「何を書いたか」というよりも「どう書いたか」という筆力が物をいうことがあります。夏目漱石の『坊っちゃん』は内容より歯切れのよい表現に惹かれるファンが大勢います。私もその一人です。『こころ』などシンネリムッツリな作品はイヤです。
『青い壺』も全体のテーマは大したことはないのですが、十四の独立した小話の書きっぷりが見事です。それぞれの小話の好みは人によって違いますが、私のお気に入りの第七話と第八話のうち、第八の一部を抜粋します。
〈(姑が亡くなって)淋しさにたえきれなくなると、厚子は実家の母に電話する。
「ねえ、お母さん、お母さんが死んだって、私はこんなに参ってしまうと思わないわ」
「ご挨拶だねえ。でもまあ結構な話ですよ。私もうちの晴子さんに、死んだあとでそう言われてみたいわ」
「晴子嫂さんは私みたいにショックを受けないと思うのよ、お母さんが死んだって。だって、うちほど大変なお婆さんじゃないもの、お母さんは」
「何が言いたいんですよ、厚子」
「だから、淋しいのよ。参っちゃったのよ。我がまま天下様のお婆ちゃんが死んだんだもんだから」
「ねえ、思えば結構な一生でしたよねえ」
「そうよ。死んだらどんなにほっとするかと思っていたのよ。だってテレビのチャンネルを変えるのだって私を呼ぶんだもの。死ぬときなんか私にフランス語で喋ったんだから」
「何度も聞くけど、なんて言ったんでしょうねえ」
「女中か売り子と間違えたんでしょ。パリかロンドンにいるような気分で死んだんだから」
「極楽往生だねえ。羨ましいこと。私はあいにく外国語を知らないから、最後は何を言うことやら。とても厚子のお姑さんみたいなハイカラな臨終とはいかないでしょうよ」
「お母さん、どうして自分が死ぬときの話ばっかりするの」
「厚子が言い出したんじゃありませんか。私が死んだってがっかりしないと言ったてでしょう。まあ、なんという娘だろう。わざわざ電話でこんなこと言うなんて」「だって淋しいんだもの」〉
大変なお婆さんは厚子さんに高価な宝石類を遺しました。それを全部身につけて夫とディナーに出かけたすきに空き巣が入り青い壺は持って行かれ、話は第九話へと続きます。
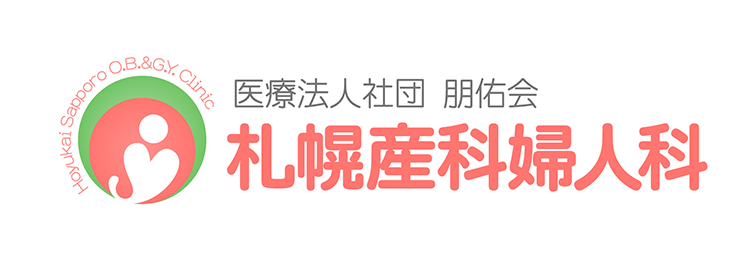
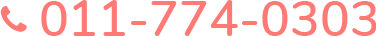









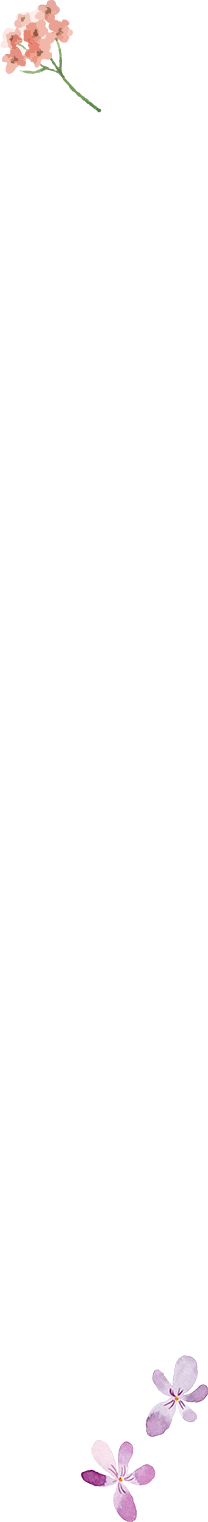
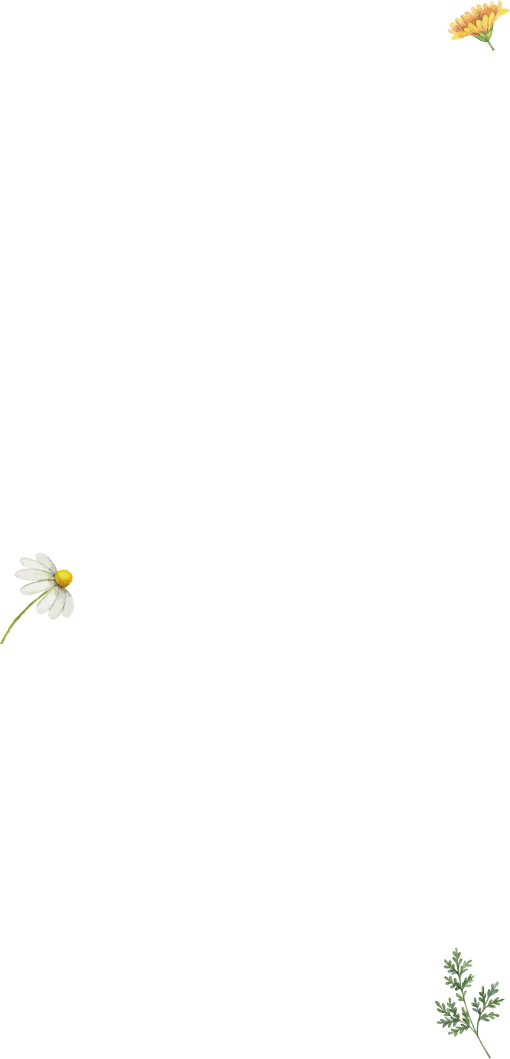
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1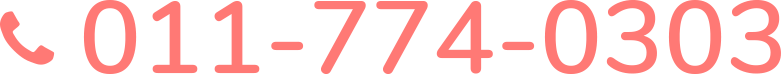
 トップページ
トップページ