高校生のとき漢文の授業に『十八史略』が取り上げられていました。同級生の本多君はその現代日本語訳の愛読者でした。「二回も読み直したぞ!」と自慢していました。私が借りて読んだところ、中国の王朝は滅んだり興ったりして同じことの繰り返しなんだなあ、と呆れてしまいました。国語の中野先生は、中国の歴代の皇帝のなかで唐の太宗(李世民)が最高の名君だね、と語っていました。かたや当時の平凡社の百科事典では清の康煕帝が歴代最高だと解説していました。二人とも漢人ではなく異民族出身の皇帝です。
最近になって『十八史略』は初心者や子供用のダイジェスト版で、日本人は本来原典に弱いので、何が良書なのか分からないんだという身も蓋もない論評を読みました。『二十四史』は正史と呼ばれる歴史書を解説しています。
正史とは歴代の王朝が前代の王朝を含めた歴史をまとめたものです。正史だからといっても「正しい」わけではありません。『三国志』も正史とされていますが、そばで記録している人間がいるはずがないのに、やたらに登場人物の演説が多く信憑性に欠けます。中国の歴史は、誰がいつ死んだなどという事実さえ押さえておけば、あとは歴史家の裁量でどう書いてもよいのだそうです。正史の始まりの『史記』も、司馬遷の情熱が入りこんでかなり文学的となり、のちの歴史家たちも解釈に苦労したようです。
『二十四史』の序章に書かれている「漢語圏の学問は、四部分類が基本である」という解説は目から鱗でした。ありとあらゆる学術・書籍は「経」「史」「子」「集」の四部、四つのカテゴリーに大別されます。それぞれ対等ではなく、「経」が第一位です。儒教に関するカテゴリーです。「史」は史学で第二位。「子」は儒教以外の諸子百家のことです。私を含めた日本人は多種多様に栄えた学問としてポジティブなイメージを抱いていますが、中国史上、ほとんどの時期はそうではありませんでした。政治の参考とならない異教邪説がはびこった時代・状況とみてきたのです。諸子百家は古代ギリシャの自然哲学に相当されます。ギリシャ哲学はローマ帝政時代に衰退して、西洋はキリスト教中心となりました。儒教をキリスト教に当てはめれば理解できますね。「集」はその他、医学、工学などの理系や作業マニュアルすべてがぶち込まれました。私のやっていることも「集」です。
「経」は儒教関係の学問と述べましたが、孔子の『論語』で終始しているわけではありません。儒教は漢で定着して、その後は漢民族の王朝(宋、明)のときに大いに発展しました。宋の朱子学は儒教に仏教などの理論を盛り込みました。明の陽明学は知行合一を旨としました。すなわち知識は行動をともなわなければ意味がないという過激な思想です。
陽明学は日本人にも大きな影響をあたえました。役人でありながら幕府のやり方に異議をとなえた大塩平八郎の乱。幕末の高田藩でガスリング砲をぶっ放して新政府軍と戦った河合継之助。みんなまわりの人に多大な迷惑をかけました。信念の塊というのは恐ろしいものです。
西洋で「経」に相当するのは神学です。昔、アイルランドでの学会に参加したとき、ダブリンの古い教会に天上まで届く膨大な書庫を見て、「こんな本、何が書いているのだろう?」と思いましたが、多分、神学関係だったのでしょう。
たしかに「経」は政治哲学の根源です。現在の中華人民共和国は、「中国共産主義」でがんじがらめになっています。
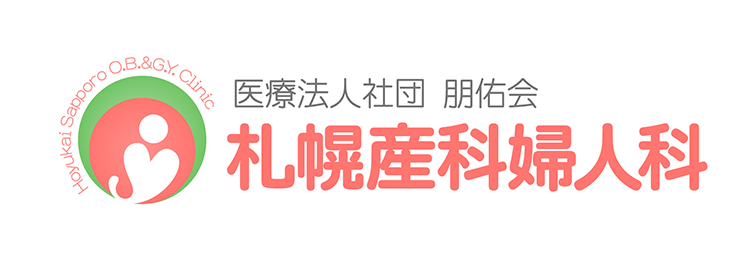
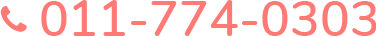









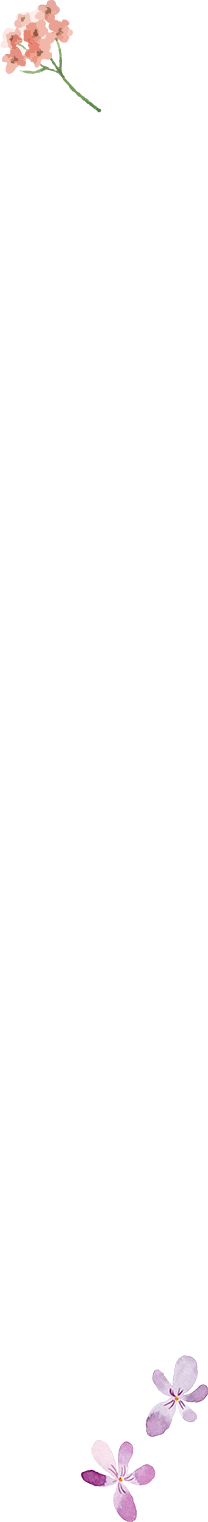
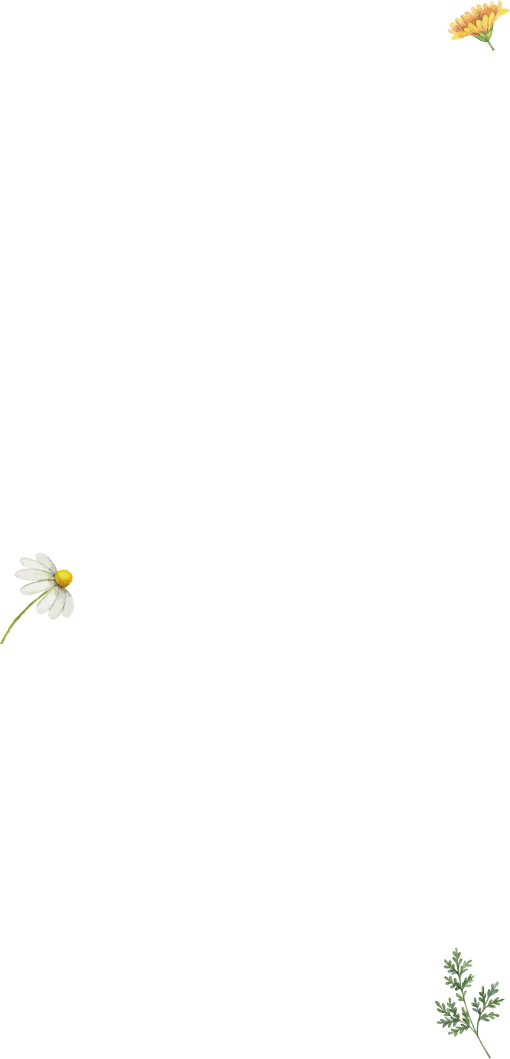
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1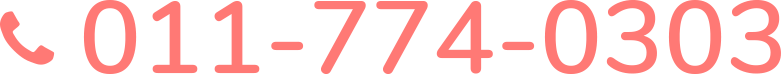
 トップページ
トップページ