私は心地良く眠りに入るため、枕もとにスマホを置いてお気に入りの音楽を聴いています。近ごろはコルトーのノクターンを聴いていましたが、あるとき同じ画面にコルトーのショパン・リサイタルがあったので開いてみました。
荘厳な演奏が始まったとたん、メロディーは中田義直作曲『雪の降る町を』となってビックリ。曲は幻想曲ヘ短調です。かぶった部分は「ゆーきのふるまちをー♪」の部分だけで、その後は分かりやすい旋律は消えて、現代音楽みたいにとらえどころのない複雑で壮大な旋律となりました。まあ、破綻したと言ってもいいでしょう。さすが大ピアニスト、コルトーは堂々と演奏しました。はじめのガッカリ感は消えてすっかり感服しました。
幻想曲ヘ短調はショパンの中では馴染みがないため、パクられていると騒がれているのは知りませんでした。しかし翌日、調べてみたら盗作とまで書かれていました。『雪の降る町を』は1952年に作曲されました。もちろんショパンはとっくに死んでいます。中田さんはこの曲がショパンとかぶっていることは本当に知らなかったそうです。
石川さゆりさんの『津軽海峡冬景色』も、ショパンのピアノ協奏曲第1番のピアノ独奏部分のメロディーにかなり似ています。しかしながらオーケストラの始まりからピアノ演奏まで間があったので、気づかれることはなかったようです。
旋律は気分の流れにそって頭に浮かんでくるので、まったく独創的なメロディーを作曲するのは無理だとピアニストの清塚信也さんが断言していました。どんなに頑張っても西洋音楽を作曲するかぎりは、バッハやモーツァルト、ベートーベンがいつの間にか入りこんでくるものだそうです。とくにモーツァルトの旋律の流れはあまりにも自然なので、当然、入りこむ確率は高いようです。
そういえば、中学生のときに、音楽の課題でオリジナルの曲を作るという宿題が出されました。当時、ピアノを習わされていたので、頭に浮かんだメロディーを五線譜に書くということはお手の物でした。30分くらいで仕上げました。気の毒に他の生徒たちにとっては大変だったみたいで、クラスのなかで提出したのは私だけでした。その曲を音楽のS先生がピアノで演奏したところ、教室のあちこちで「なんか聴いたことのある曲だぞ」とささやき声がしました。
たった30分で思いついた曲です。パクリようがありませんが、誰か有名な作曲家のメロディーと重なったのでしょう。
「そうか、オレはそんな名曲が作れるんだ」と変な自信を持ちました。
最初から最後までパクるのは芸のないことですが、いい加減なところでメロディーを換えて、さらに変調すれば文句は出ないでしょう。『雪の降る町を』も「おーもいでだーけがとーりすぎてゆーくー」からはオリジナルで、「とーいーくーにーかーらーおーちてーくる」になると短調から長調になり、その後、短調にもどったり長調になったりして終わります。
私は中田義直さんの自然なメロディーが好きです。とくに『夏の思い出』など変調する部分がジーンときます。童謡として有名な『めだかの学校』はあまりにも自然なので、1951年作なのに、「自分の子供の時分から歌われていた!」と主張する明治生まれのお年寄りがかなりいると、生前、中田さんはテレビのインタビュー番組で笑っていました。
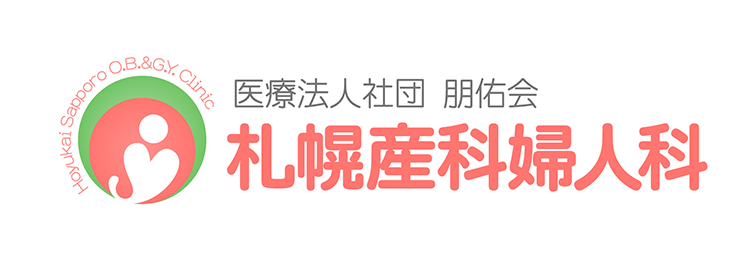
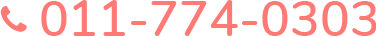









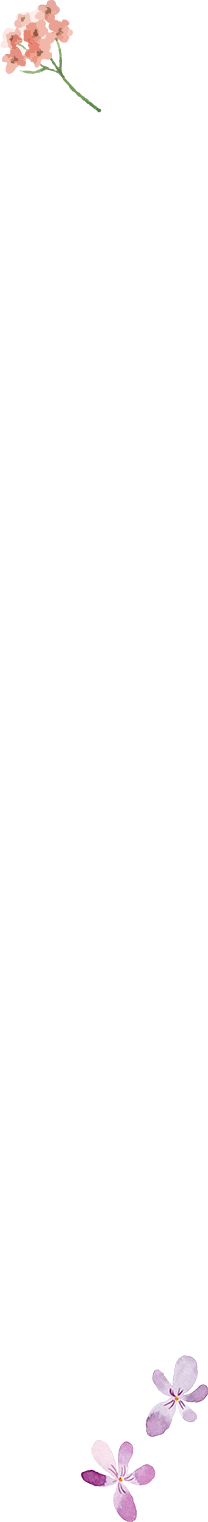
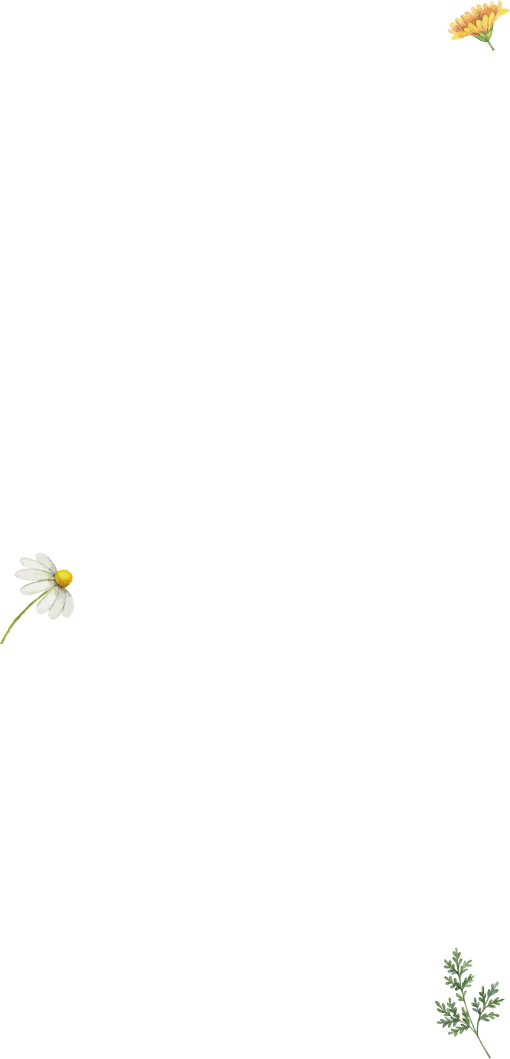
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1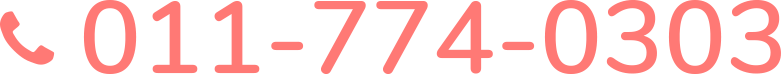
 トップページ
トップページ