朝日新聞の「人生の贈りもの」で田嶋陽子先生がフェミニストとしての憤慨の人生を語っていました。世間の期待を裏切って実生活では一流の男性にもてていたようです。小泉純一郎元総理はエレベーターで一緒になったさい敬意を表してくれ、フェミニスト代表としてあえてバラエティ番組に出演し、イジクリ役のビートたけしさんと表面上はケンカしていましたが、たけしさんの本当の繊細さを認識したり、右翼番組『そこまで言って委員会』でもやしきたかじんさんや三宅久之さんからリスペクトされていました。もともとはお母様からの束縛がその後の人生に大きく関与したようでした。46歳になってお母様の束縛がとれ、精神的には自由になりましたが、フェミニストとして戦い続けています。そのご意見はごもっともですが、私としては何か居心地の悪さを感じてしまいました。
たとえばお茶くみ。田嶋先生は「どうして女ばかりにお茶くみさせるの?」と怒っていますがお茶くみのどこが悪いのでしょうか?お茶くみで有名な話(たぶん作り話)として豊臣秀吉が鷹狩りで咽が渇いたためある寺でお茶を所望したさい、小坊主でのちの石田三成が一杯目は大ぶりな茶碗に温めのお茶を、二杯目は中くらいの量で、、三杯目は上等なお茶を熱々で提供し、秀吉を感心させて出世街道の出発点としました。またその頃から茶の湯がさかんになり、お茶くみは茶道として芸術の域まで昇格しました。
さらにトイレ掃除。カンヌ国際映画祭で主演男優賞に選ばれた役所広司さん主演『PERFECT DAYS』では公衆トイレでの掃除を修験僧のように淡々とこなす姿が世界中の映画ファンの評価を得ました。
男性優位をしかる田嶋先生は、知らず知らずにお茶くみやトイレ掃除を二流の仕事として差別しているのではないかと考えてしまいました。九州大学心療内科初代教授の池見酉次郎先生は、「禅では座禅だけが修行ではないのですよ、庭の掃除、食事の用意、後片付け、生活しているすべてが修行なんですよ」と言われていました。
ノンフィクションライターの沢木耕太郎さんは、田辺聖子さんを取材しているうちに「べつにテッペンとらなくたってええんやないの、三合目ふきんやふもとならではの楽しみや喜びだってあるのに」という言葉に軽い衝撃を受けました。沢木さん自身、知らないうちに「テッペン」を目指していた自分に気づいたからです。
私は中学生のとき、ディケンズの『オリヴァー・ツイスト』を読みました。小説の終わりころ準主人公が「自分は、これからは家庭第一に生きる!」と宣言した場面で、何と覇気のない男だろうと呆れました。時代は大英帝国が最盛期のビクトリア朝です。ほとんどの英国ジェントルマンはイケイケで活躍していました。
最近、進化や生態系を調べているうちに人類本来の生き方が見えてきました。健康で争いのない世界を目指すのが一番大事だということです。古代の中国の人々は叡智にあふれていました。平和な治政を「鼓腹撃壌」という言葉で表現しました。高校生のときに漢文で習いましたが、血の気の多い若者には何が良いのかしっくりきませんでした。
現在の日本のジェンダー・ギャップ指数が低いのは「政治参画」と「経済参画」が他国に遅れているからだそうです。ディケンズの言うように「家庭が第一だ」となれば相対的に政治と経済の重要性は低くなります。ジェンダー・ギャップ指数が低いのは平和だということです。何の問題があるのでしょう。
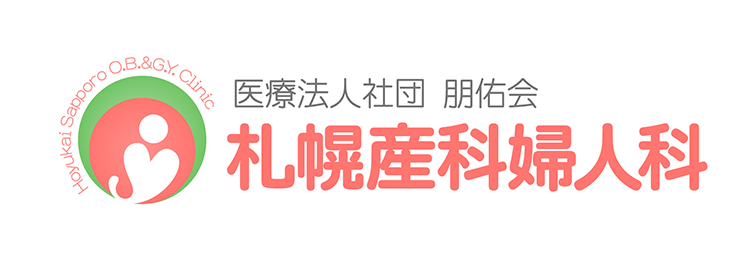
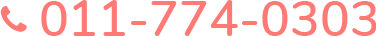









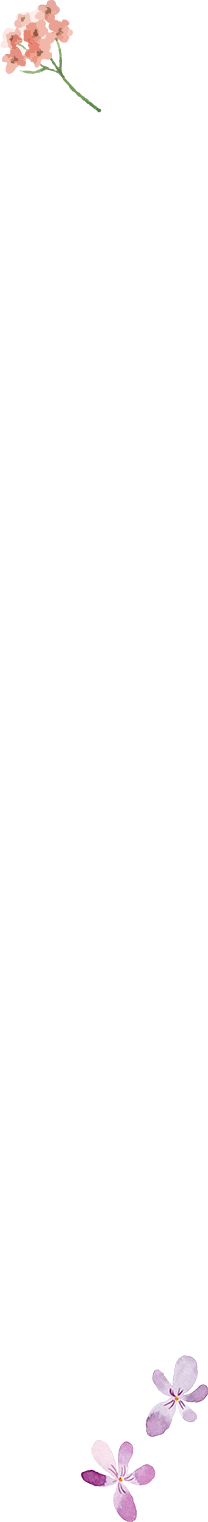
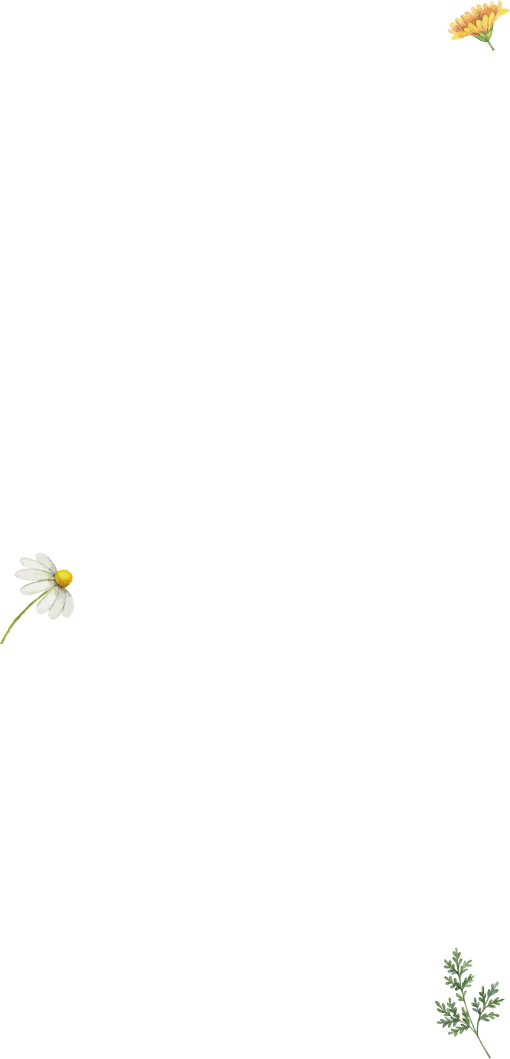
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1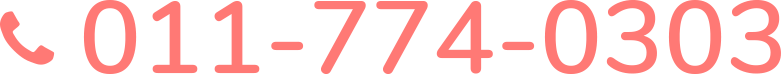
 トップページ
トップページ