脳は何のためにあるのでしょうか? たいていの人は考えるためだと答えますがそれは間違いです。脳は主に運動を制御するために働いています。運動しない動物には脳は存在しません。脊索動物のホヤは幼生期は魚のように泳いでプランクトンを食べます。プランクトンを捕らえるには脳によって運動をコントロールする必要があります。そして栄養豊富な岩場にたどり着くとそこに根を張り餌が流れてくるのを待つだけの体となります。脳は役目を終えて吸収されてしまいます。
脳はコストのかかる臓器です。ホモ・サピエンス(現代人)とほぼ同時に出現したネアンデルタール人の脳はホモサピエンスの脳よりも大きかったようです。コストのかかる脳を維持するためには高カロリー食が必要です。両者とも食料を得ることが困難な氷河期を体験しています。その結果、コストのかかる脳が重荷になってネアンデルタール人は消えていったと考える考古学者もいます。
大昔の人々は、道具を作り、狩猟をしたり、火をおこして得た食料を煮炊きしたり、移住をせまられたりしました。それらはすべて手仕事で解決しなければなりませんでした。
大変な労力です。その後、農業が発明され、仕事が分業化するにつれ、すべて自分で解決する必要は無くなりました。ただし農業をするには自然の摂理を理解し、農作業をする技術を開発しなければなりません。このあたりでは脳はフル回転しています。ただしいったんノウハウが出来上がると人々はそれにしたがって行動するので生活はラクになりました。その後、文字の発明によってノウハウは記録され、人々の苦労は少なくなりました。脳の出番は少なくなりました。事実、一万年前から脳はだんだん小さくなりました。
文字の登場で知恵は蓄積され頭が良くなったと主張する人もいますが、体を使う方が考えるよりも脳の力が必要です。数字も計算する手間をはぶくのに絶大な効果を発揮しました。あるロボット工学者は、コンピューターで分析するよりも、よろけた子供が体制を整える技術の方がはるかに複雑だと言っています。囲碁将棋の領域では、AIの方がプロたちを負かすようになったではないかと反論する人もいるでしょうが、あれはただ碁石や駒の位置を指定するだけです。もし、駒や碁石をロボットに取り出させて指してみろと言われたら、AIは現在のところ何もできません。若い将棋のプロや囲碁のプロはAIを活用して学習していますが、このような実戦となればAIに負けることはないのです。
現在の人類は文明の恩恵を受けていますが、ほんの少数の発明家のおかげでスマホやAIを活用しているだけで、自然の中に放り出されれば何もできません。恐竜学者の小林快次先生はモンゴルで恐竜の大きな化石を発見しましたが、それをトラックに収納するにあたりクレーンをはじめとした重装備を持ちあわせていなかったので途方にくれました。そこで頼りになったのが現地のモンゴル人の研究者たちでした。素朴な工夫で2トンもあるサンプルをトラックまで移動させてしまいました。また彼らはヒマさえあれば相撲をしてとてつもない腕力の持ち主でした。小林先生が果敢に挑んでも一度も勝てませんでした。
私は地下鉄を愛用しています。他の乗客を見るとほとんどの人がスマホとにらめっこしています。まるでスマホが脳の一部となり、体から外に飛び出しているんではないだろうかという印象を受けます。実際に若者の中には自分で考えることをやめて、SNSで知り合った輩を信じて他国に売り飛ばされてしまうという世も末現象が生じています。
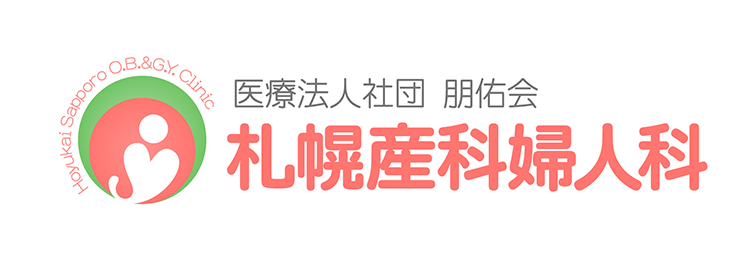
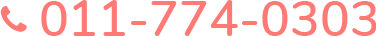









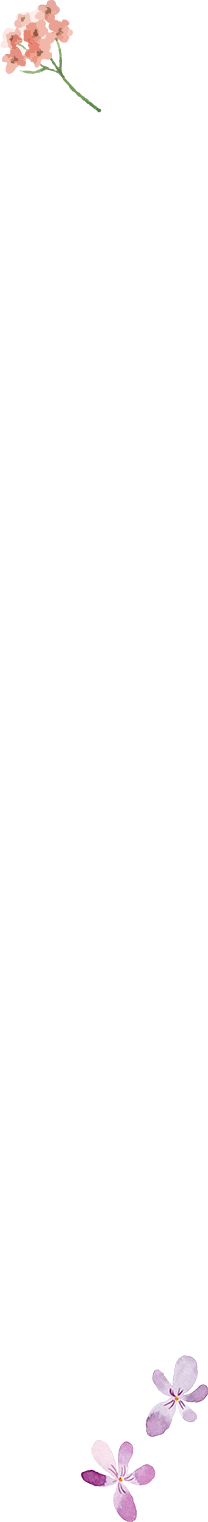
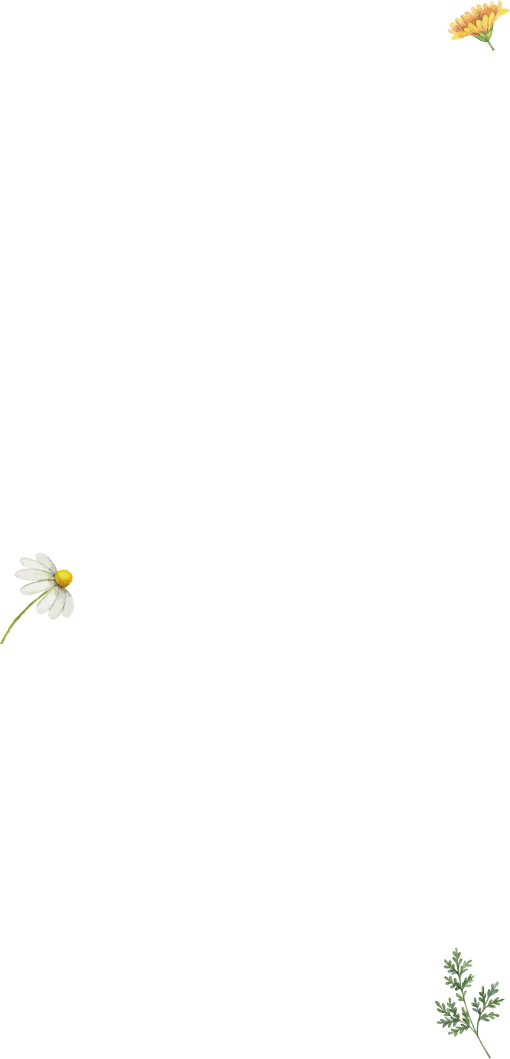
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1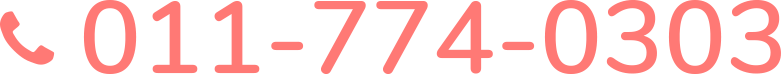
 トップページ
トップページ