本来、人類は狩猟を糧としてきたので炭水化物を摂るべきではない、と主張している人たちがいます。『炭水化物は人類を滅ぼす』を書いた夏井 睦さんや『GO WILD』の著者ジョン J.レイティ博士など。人類は1万年前に農業を発明して、穀物を中心とした炭水化物を食料に加えました。そのおかげで人口も増えたし一見めでたしめでたしなのですが、糖尿病や癌といったそれまでにはなかった病に悩まされるようになったというのです。
私は、成功した生物とは個体数の増加を基準として考えているので、これらの説には全面的に賛成しかねるのですが、糖尿病が炭水化物の制限でコントロールされている事実を見て、ある程度は評価しています。
レイティ博士は、ただ肉食すればよいわけではないと述べています。筋肉だけでなく脂肪も内臓も、ようするに糧とする動物は丸ごと食べるべきと主張しています。これは納得できます。海洋生物の頂点にたつクジラの仲間はイルカも含めて、丸ごと胃袋に納めて長寿を誇っています。レイティ博士はネアンデルタール人が滅びた原因として魚を食べなかったと述べています。陸上の生物は性格範囲が限られているので、体内に蓄えられている栄養分にも偏りがあるのに対して、魚、とくにサーモンは広い海で生活して、さらに川をさかのぼって限りない種類の栄養素を蓄えているはずなので、これは是非とも食べるべきだと主張しています。今の人類でもそんなにサーモンの恩恵にあずかっている人たちは限られています。これは単なる机上の空論です。
とりあえず議論をもとにもどしてみましょう。有史以前の人類の食生活は歯の構造から知ることができるそうです。これによると確かにネアンデルタール人もわがホモ・サピエンスを肉食が基本ということです。歯の構想から食生活を推察した例としてはスウィフトの『ガリヴァー旅行記』があげられます。大人国で捕らえられたガリヴァーは歯の構造から肉食と判断されました。当時、私は、ヒトは前歯が上下で8本、犬歯が4本、臼歯が20本、したがって草を2、肉を1、穀物を5の割合で食べるのが正しいと教わっていました。これは当時の日本人の食生活を反映していてそれなりに説得力がありました。穀物5ですからご飯は必ずお代わりしたものです。それに対してガリヴァーは肉食だというのでイギリス人の歯の構造はどうなっているんだろう?と中坊の私は不思議に思いました。
ほぼ同時期に読んだディケンズの『オリバー・ツイスト』に「ひさしぶりに肉が食べられる」と喜んでいる場面があったので、イギリス人の肉好きを知ることができました。かたや中国。『孔子』に「素晴らしい音楽を聴いて肉の味を忘れるほど感動した」という記載があります。古代から中国人も肉好きでした。
さらに議論をもどします。ヒトを含む霊長類のほとんどは草食を主としています。しかし、歯の構造はニホンザル、ヒヒ、チンパンジーなどヒトよりもずっと立派な犬歯を有しています。綿密なフィールドワークによってニホンザルが川魚を捕って食べたり、チンパンジーが肉食をしているのが観察されています。
肉食目とされているクマ科のツキノワグマの実態は9割が草食で、ヒグマもそうそう肉にありつけることはないようです。パンダにいたってはほとんどが竹です。しかし、もしパンダが化石になったら、歯の構造から肉食と判断されるでしょう。このよう生物には適応力があります。環境に応じて人の食べる物もいくらでも変化すると私は考えています。
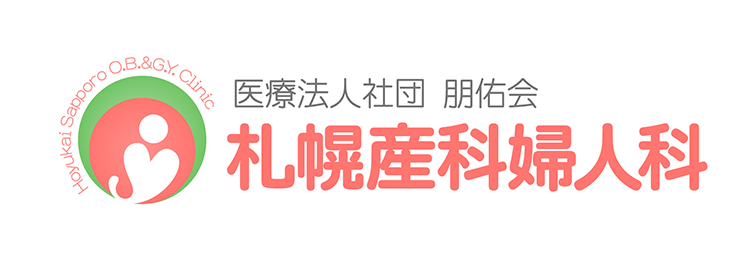
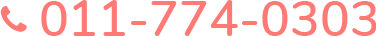









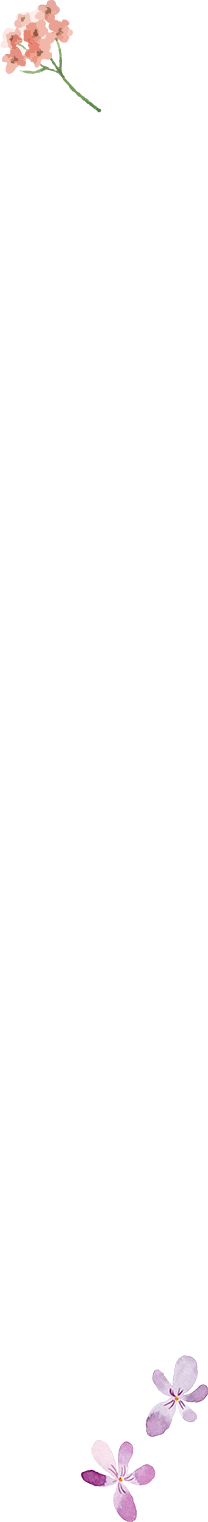
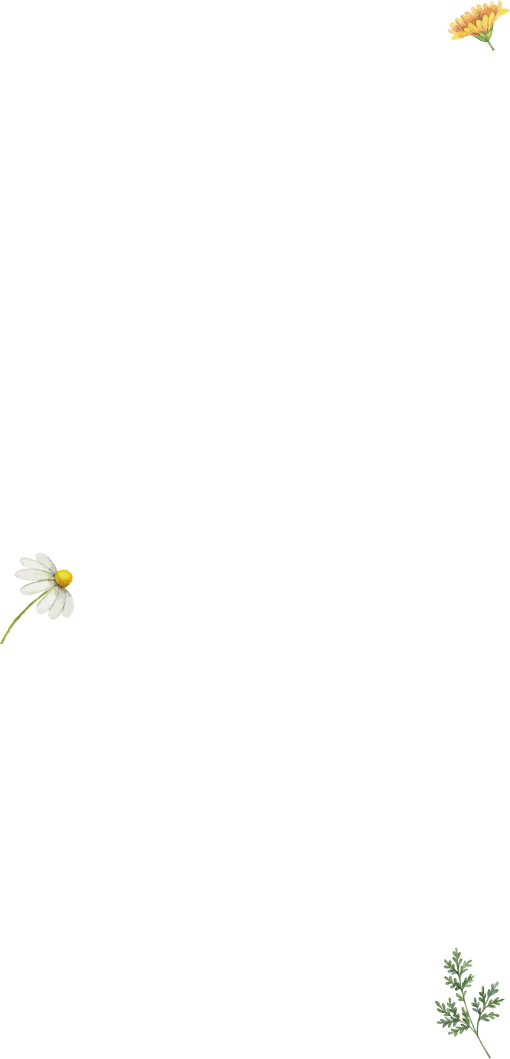
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1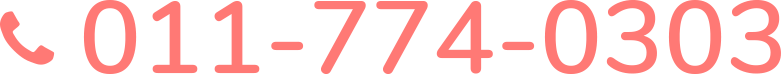
 トップページ
トップページ