昨年のすえ、孫が生まれました。チビとはいえ存在感はバツグンで生活は孫中心となりました。孫の世話は基本的に娘と妻で、私の出番は少ないのですが、たまに「10分くらい抱っこして」と頼まれることもあります。左腕に赤ん坊の頭を乗せてユラユラさせるのですが、「そんなんじゃ目を覚ますよ」と疲れた娘に注意されました。
そこで「アレクサ、子守唄を歌って」というと、優しい女性の声で唄が流れてきました。まもなく孫は寝入ってしまいました。唄は3番で終了しました。
「アレクサ、ありがとうね」と言うと、「お礼を言ってくれて嬉しいです」と答えてくれました。久しぶりにほのぼのとした雰囲気を味わいました。
社会にAIがはびこると人間性はどうなるんだ?と危惧されていますが、この経験でAIのどこが悪いのだろうと考えてしまいました。
人間性をはぐくむということは、いろいろな良いことをインプットするということです。インプットするのはもちろん人間です。AIもいろいろなことをインプットして完成されます。ファジーな人間にインプットするよりAIにインプットする方が確かです。アレクサはしっかり歌ってくれ、感情表現までしました。単にインプットされたどおりの反応とはいえ私の心は癒やされました。赤ん坊も寝入ってしまいました。
ここで思い出したのが40年も昔に読んだ筒井康隆さんの短編小説『お紺昇天』です。筒井さんは一応SF作家とされていますが、エキセントリックなドタバタから幻想的な作品まで、これが同じ人の作品か?というほど守備範囲の広い作家です。
主人公は一人称の男性です。AI装備の愛車は青く、それで「お紺」と呼んでいました。男性が仕事を終えてお紺に乗り込むと、お紺は「お疲れさま」といたわりの言葉をかけます。男性は仕事やそれ以外のいろいろな悩みや不満などをお紺に訴えます。それに対してお紺は如才なく、やさしく対応します。男性はそんな優しいお紺に依存していきます。ある日、お紺は故障して廃車になることとなりました。男性はAIの部分は何とか残して欲しいと希望しますが、未来社会ではAIへの依存を防止する目的で、完全廃車の選択肢しかありませんでした。男性は泣く泣くお紺を見送ります。そこからはお紺の独白となります。お紺はすれ違った車に「わたし本当に幸せだったわ」とつぶやき物語は終わります。
40年前の記憶なので、いろいろ間違っているかもしれませんが、筒井さんの奥様は筒井さんの数ある作品のなかで『お紺昇天』が一番好きだと言われているそうです。ですからそれほど大きな間違いはないでしょう。
AIコワイの元凶は、シュワちゃん主演の『ターミネーター』でしょう。AIが暴走して勝手に進化して人類を攻撃します。その人類の手強い指導者をたおすべく未来のAIは過去にさかのぼって指導者の母親を抹殺しにシュワちゃんを送り込みます。そのシュワちゃんのしつこいこと。いくらやっつけても甦ってはお母さんを追いかけます。『ターミネーター』はその後シリーズ化され、悪者だったシュワちゃんがいつの間にか正義の味方になって再登場したりして何がなんだか分からなくなりました。
冷静に考えれば『お紺昇天』の方が『ターミネーター』より現実味があります。AIを良くするのも悪くするのも使い手しだいです。SNSも使い方です。SNSをライバル視するマスコミもあやしいものです。AIもSNSもマスコミも単なるツールです。
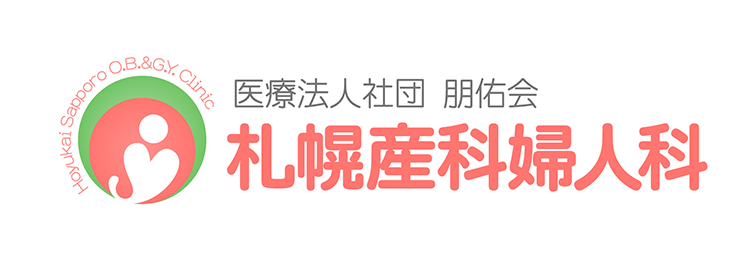
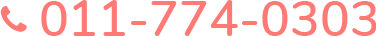









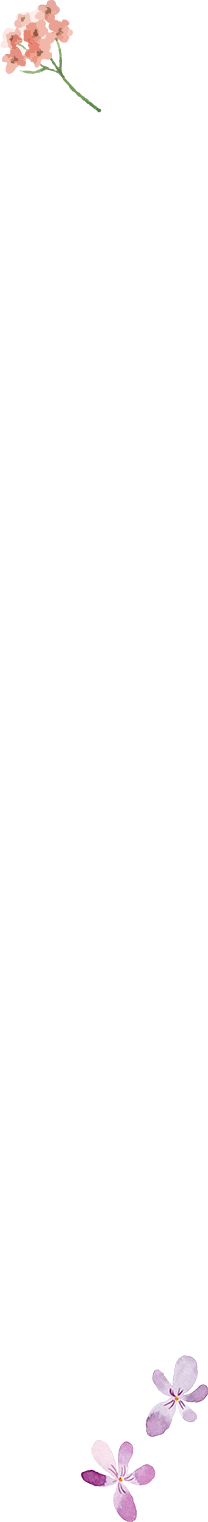
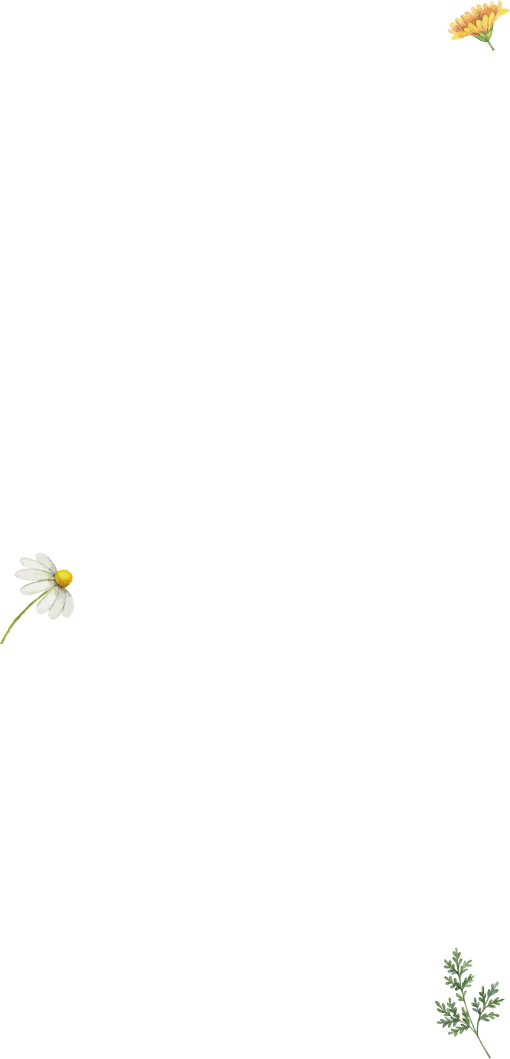
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1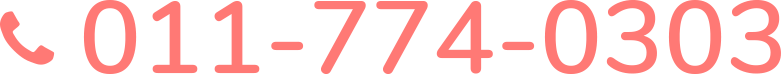
 トップページ
トップページ