朝日新聞と讀賣新聞の第一面の広告欄に載っていた本です。13歳からの考古学シリーズ第5弾です。広告を見たときの感想は、こんな本売れるんだろうか?でした。空や海など世界は青で囲まれているのに、それを表現する顔料や染料を作るのが困難で、人類は大変な苦労をしてきたというのです。ちょっと気になるので結局買ってしましいました。
子供の頃の私は、青には興味はなくもっぱら赤をもとめていました。まだ3,4歳のとき、デパートの屋上の遊園地で、1人乗りの車を選ぶさい「赤じゃないとイヤだよう」とひっくり返ってダダをこねた記憶があります。もちろん空の色は昼間の青よりも夕焼けの赤に惹かれました。
ティーカップの色もなぜ圧倒的に青が採用されるのか不満でした。赤にしろ! 青に惹かれるようになったのは、中学生のときに観た映画『隊長ブーリバ』で、コサックの父を裏切りポーランドに寝返った次男が青の軍服をまとって登場してからです。格好良かった。その後、裏切り者の次男は父ブーリバに殺されました。
男性用の和服は藍染めが主流です。何かの事情で藍染めの着物を着たことがありました。東京の叔母さんがしきりに「紺は良いねえ」と褒めてくれましたが、どこが良いのかサッパリ分かりませんでした。スーツは、鈴木知事は青一色できめていますが、私は不思議と青は似合わず、茶系でおしています。
一番気に入っているのはデニム地で生成りのスーツです。襟無しでカジュアル。正式な会合には向きませんが懇親会には最適です。以前、東京の明治神宮で次女の婚約相手とその両親に会うというので、それを着て行ったら妻に「そんなラフなかっこうをして!」とこっぴどく叱られました。結納だったのです。それならそうとハッキリ言ってよ。発達障害のグレーゾーンである私は、察しがつかないことが多々あります。
神代の時代(はにわ時代)の人々はもっぱら麻の生成りを着ていました。その後、飛鳥時代や奈良時代の貴族は貴重な衣服を染めるのに苦心してきました。ジーンズなんかどうでもいいのにインジゴブルーが主流で、とうとう私もこの歳になってもはかされています。ジーンズは生成りだと汚れが目だつので、しょうがありませんね。
さて、この本はなんせ13歳向けなので、漢字という漢字は、「見る」や「聞く」もすべてルビがふられています。そのため、書店で買い求めたとき、売り場は子供向けでした。登場人物は中学1年生の男子2人と、その片方の母親、それに母親の恩師で少年たちを指導する元大学教授、そして母親と大学で一緒だった美術館の研究員とそのアシスタントです。父親は最後まで登場しなかったので、お母さんはシングルマザーなのかな?とよけいなことが気になりました。元教授は「そうじゃのう」とか「わし」とか岡山弁で話していました。設定は夏休みの課題研究で、元教授の森井老人の指導で人類が青を手に入れるためにどんな苦労をしたか、実験などをとおして実証します。少年たちは元教授を森井老人とかげで呼んでいますが、中坊が「老人」なんて言うかねえ・・・。「ヒゲジイ」みたいに「森ジイ」の方が自然だと思うんだけどなあ。
著者の谷口陽子さんと髙橋香里さんは保存美術などの専門家です。今回、13歳の中学生が理解できるようにと小説仕立てで執筆しました。ですから話の流れは不器用な印象を受けましたが、けっこう読まされました。中学校の図書室には必須な本だと思います。
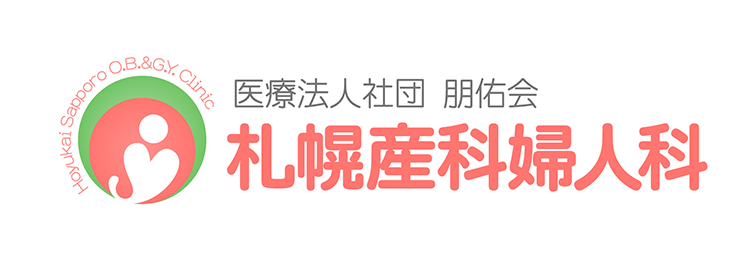
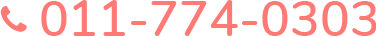









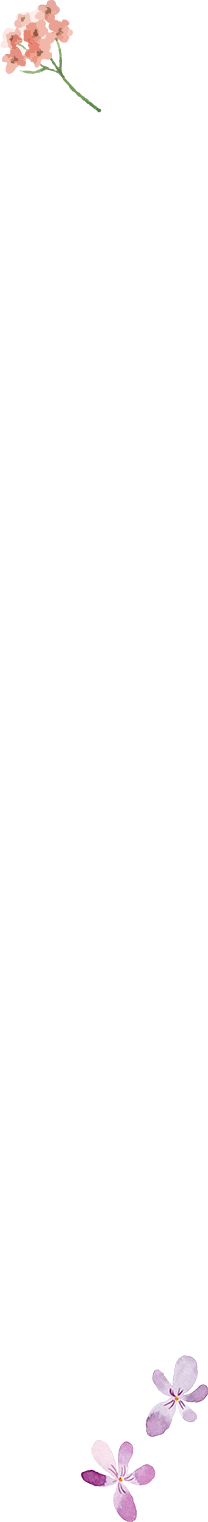
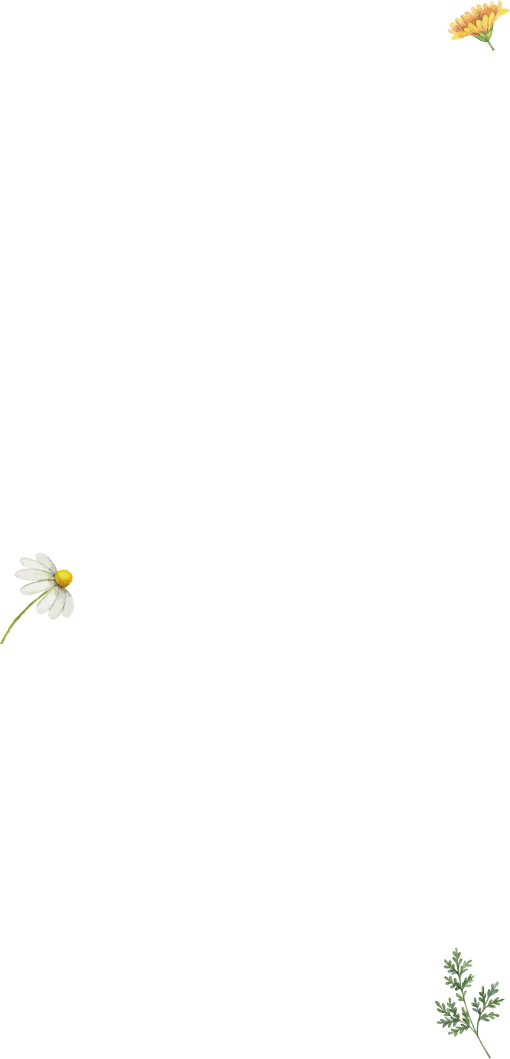
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1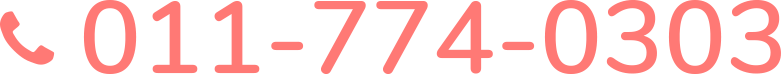
 トップページ
トップページ