なかなか症状が改善しない患者さんが内科医からそう言われたそうです。
「その先生、医者に向いていないんじゃないですか?」
思わず口からそんなセリフが出てしまいました。学生のとき、「前医をそしらず」という言葉を習ったのに頭に血がのぼりました。
症状は動悸とあちこちの痛みです。精神科の先生も体が痛いと言って受診されても途方にくれることでしょう。
実は心身医学の歴史でも身体的な症状に対してそれに対応する検査データーがないとき、精神科の医師に介在してもらうといった対処法が流行したことがありました。リエゾン医学といってアメリカを中心に行われました。当然、日本の心身医学会も影響を受け、日本心身医学会総会のシンポジウムに取り上げられたことがありました。
シンポジストの著名な先生たちはほとんどがリエゾン医学には懐疑的で、なかには「主治医に、『おばあちゃん、今日の具合はどうですか?』とやさしく言葉をかける方が何倍も良い」と言い切る先生もいました。
西洋医学には身体とメンタルを区別する伝統があります。かたや東洋医学では「心身一如」が基本です。具体的には「肝」を病むと怒りが生じ、「心」が病むと笑いが生じます。この笑いは楽しい笑いではなく追いつめられたときの空虚な笑いです。「脾」を病むと思い悩み、「肺」を病むと憂い悲しみます。そして「腎」がやられると恐れが生じます。「肝」、「心」、「脾」、「肺」、「腎」は五臓といい、西洋医学的に相当する臓器には肺以外はあてはまりません。江戸時代に杉田玄白や前田良沢などが『解体新書』を書くにあたって単なる哲学的な概念と判明し、バカにされるようになりました。
私も東洋医学の勉強会で、「臓腑弁証などは空論みたいでイヤだ、生薬の構成にしたがって治療方針を決めたい」と青臭いことを言ったら、師匠の下田憲先生が完爾と笑いながら「約束事として覚えておいた方が便利だよ」とたしなめられました。
イヤだイヤだと言っているうちに、時間がたつにつれ臓腑弁証はなじんできました。あるとき、若い女性が不正出血のため受診しました。子宮の出口からは確かに少量の出血はありましたが超音波検査では異常はありません。何だか沈んだ様子なので、「ちょっといいですか」と言って手首を見せてもらいました。はたして浅くて新鮮なリストカットがありました。そこを撫でながら「いろいろ大変だったんだね」と言うと、女性は涙を流しました。それ以上は深追いしないで、六君子湯という体力を補う漢方薬を処方しました。1週間後、女性は明るい顔をして受診しました。がん検診はOKで出血も止まっていました。
はるにれ薬局の後藤先生が「どうして子宮出血に六君子湯なんですか?」と訊ねました。
「脾虚だからですよ」。この一言で後藤先生は納得しました。確かに臓腑弁証は便利です。
脾虚とは体力が落ちていることです。そうすると気分が落ち込みます。心もやられてくると心脾両虚といって不眠や抑うつ気分が顕著になります。こうなると帰脾湯という薬の出番になります。この女性はここまで落ちてはいないと当時の私は判断しました。
精神科医でもタフな先生がいて、下腹部痛のため産婦人科、消化器内科とも異常がないと言われた女性の治療を10年もされました。結局、当院を受診して鎮痛薬や向精神薬などを動員して半年足らずで改善しましたが、しぶとい先生だなと感心したことでした。

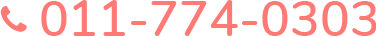




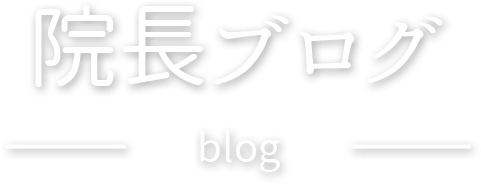




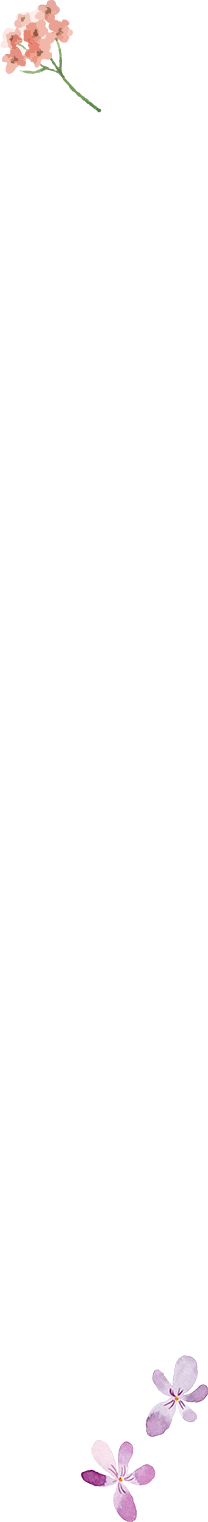
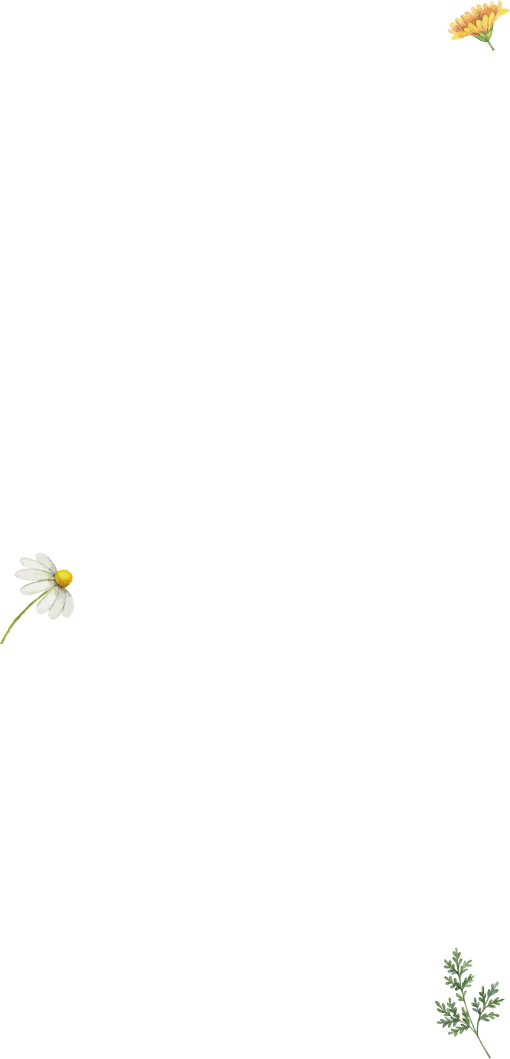
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ