お腹の赤ちゃんが大きいわりに小柄な妊婦さんに訊きました。
「ご自身は何㎏で生まれたんですか?」
ほとんどのお母さんは正確に答えてくれます。小柄な女性でも大きく生まれた場合はよく見ると骨盤は大きそうで、これなら帝王切開しなくても大丈夫だな、と安心します。
実はかく申す私は自分の出生体重を知りません。ついでに2歳年下の妹に確認しても「そんなもの知らないよ」とのこと。当時は尺貫法だったため正確な記録がないのです。
ではどこで生まれたのかと言うと自宅でした。取り上げたのはベテランの産婆さんでした。しかしながら昭和30年代になると急激に産科医のいる施設での分娩が多くなり、出生時の記録も確かとなりました。ハイ、私たち兄妹はそれ以前に生まれたのでした。
正式には昭和23年から産婆さんは「助産婦」と改名されたのですが、世間一般では開業助産師は産婆さんと呼んでいました。しかし、産婦人科のいる病院や産院に勤務する場合はモダンに助産婦と言うようになりました。
その後、助産婦の時代は続き、平成14年から看護婦および保健婦が看護師、保健師となるとともに助産師となりました。当時の師長Sさんははこれがイヤで、みずからは助産婦と言ってはばかりませんでした。この師長(もとい!自分では定年まで婦長と言っていました)のこだわりはもっともなことで、いまだに日本では男性は助産師の資格は取れません。そんなにお産がしたければ産科医になれ!というのが日本の風潮です。
助産師は看護師の資格を習得した後、さらに専門教育を受けて国家試験によって資格が得られます。正常分娩は医師が立ち会わなくても行えるので、基本的に産科医はラクチンでした。この傾向は北大が札幌医大よりも著しく、夜間、お産で赤ちゃんの心拍が落ちて早く出す必要が生じたときに当直の産科医がなかなか起きてこないため、いち早く分娩室に登場した小児科医が産婦さんのお腹を押して赤ちゃんが出したことがあったと聞きました。もちろん今の北大の産科医はやる気満々の先生ばかりなので心配ありません。
昔、鹿児島で母性衛生学会が開催された際、シンポジウムで伝説の産婆さんの講演がありました。その施設には分娩監視装置などといった物はありません。しかし、産婆さんは産婦さんが入所してからずっと附き添っていました(英語のmidwife の語源はまさに女性に附き添うという意味です)。そして赤ちゃんが弱っていることを知り、「今すぐ、大学病院に行って帝王切開をしてもらいなさい!」と夫に言いました。しかし、大学病院でモニターを附けても異常はないと言われてスゴスゴと帰されました。産婆さんは怒り、さらに「もし帝王切開しないで赤ちゃんに異常が起きたら訴えると言いなさい!」とプッシュしました。大学病院でシブシブ帝王切開をしたところ、はたしてしんなりと弱った赤ちゃんが産まれました。産婆さんの言うことはまさに正解でした。
さて、どうして大学病院で分からなかったことが産婆さんには分かったのだろう? その後しばらく考えました。赤ちゃんの心拍の連続モニタリングよりも信頼度が高いとされる検査があります。超音波で30分以上赤ちゃんを観察する方法です。要するにただじっと見ているだけ。赤ちゃんがクッタリしていれば危ないサインです。きっと産婆さんはお母さんのお腹にずっと手を当てていて赤ちゃんの動きが鈍いことに気づいたのでしょう。ただし、はっきりと言語化できず、長年の勘として神秘的な発言となったのだと思います。
第354回 忙酔敬語 産婆さん

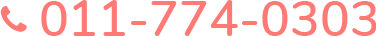




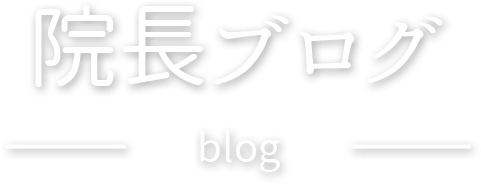




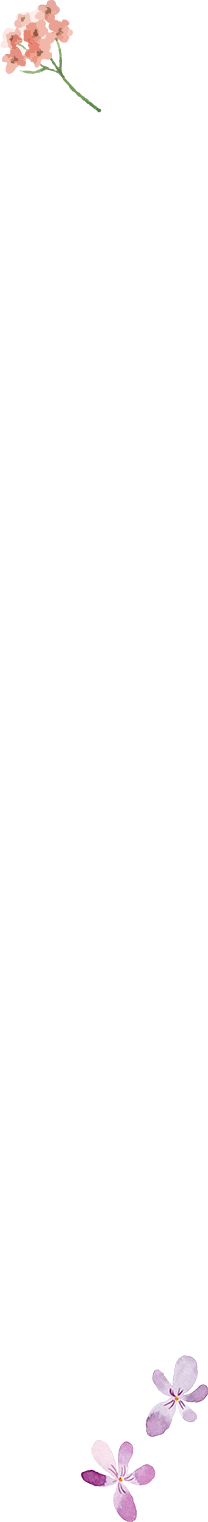
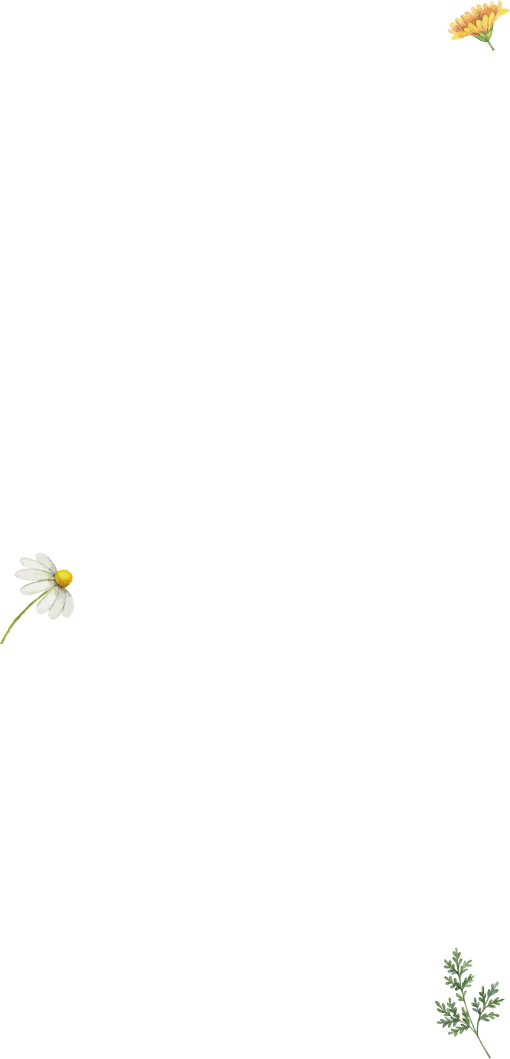
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ