現在、医療には超音波診断をはじめ、CT、MRI、PETと画像診断がどの施設でも行われているか、あるいは他施設へオーダーされるようになりました。
今、考えると空恐ろしいかぎりですが、昔は、産婦人科の領域では内診のみで治療の方針が決められていました。
私が札幌医大産婦人科の医局長のとき、術前の教授の内診によって術式や執刀者が決定されました。手術の助手や外回りを決めるのは医局長の仕事です。
超音波の性能もあやしげで、CTは脳外科や整形外科では行われていましたが、軟らかい組織が主である産婦人科領域には不向きで、まだMRIは普及していませんでした。
他科からは、産婦人科医の手には目がついているのか!と内診力は高く評価されていましたが、やはり限界があり、卵巣腫瘍と診断されていたのにいざ開腹してみると何もなかったり、子宮筋腫だったはずが卵巣腫瘍だということはめずらしくはありませんでした。
あきらかにお腹がふくれている大きな子宮筋腫の患者さんがいました。当然、開腹手術かなと思っていたら、念入りに診察した教授はおごそかに言いました。
「子宮の動きは良いし癒着はないようだ。これは経験があれば腟式子宮全摘術でいけるな。佐野君、君がやりなさい」
教授に買いかぶられたことは名誉ではありましたが途方にくれました。助手には気の利く医師を指名して輸血することなくやり遂げました。子宮の大きさは800g以上でした。
40年近くも昔は、産科の健診はお腹を触って赤ちゃんの位置を確認して、トラウベという実に原始的な聴診器で赤ちゃんの心拍を確認して、血圧など異常が無ければ良しとしていました。トラウベは単なる木の筒のような聴診器ですが、一般に使用されている膜型の聴診器では波長の関係で赤ちゃんの心拍は聞こえません。お腹にじかに耳を当てても聞こえるのですが、さすがに気持ち悪がられるのでできません。
なんせ、お腹を触ってトラウベを当てるだけなので妊婦健診はアッという間に終了。お産の多かった時代でしたから、時代にそくした診療ではありました。
先輩から「赤ちゃんの位置も正常だから後は頼んだぞ」と言われた産婦さんのお産が進み、いよいよ赤ちゃんの一部が見えてきました。しかし、それは頭ではなくお尻!
「先輩の嘘つき!」と毒づきながらも何とか無事に赤ちゃんは産まれました。
最近はどの診療科でもCTやMRIを多用するようになりました。それは悪いことではありませんが、患者さんをじかに触れることが少なくなり、画面ばかり見て患者さんの顔を見ないという人間味のない診療が問題視されるようになりました。
東洋医学では四診といって、患者の全体の印象をとらえる「望診」、聴覚と嗅覚による「聞診」、言語による「問診」、患者を触れる「切診」が基本的な診断法です。
中国の歴史書『史記』には扁鵲という医師についての記載があります。仙人に気に入られて秘薬を授けられ、それを飲んだところ病人の五臓の病変がすべて見えるようになり、伝説の名医となりました。
視覚はなんだかんだ言っても人間にとって最大の情報源です。
意味合いはちょっと違いますが「百聞は一見にしかず」という言葉もあります。
古代から画像診断へのあこがれはあったようです。
第298回 忙酔敬語 画像診断へのあこがれ

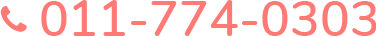




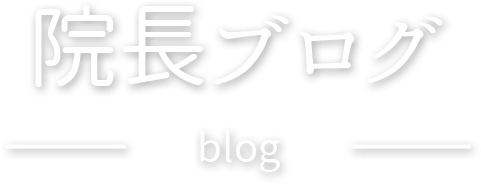




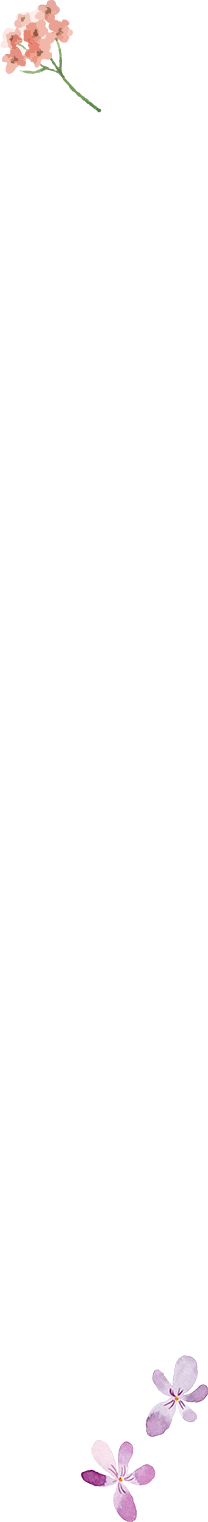
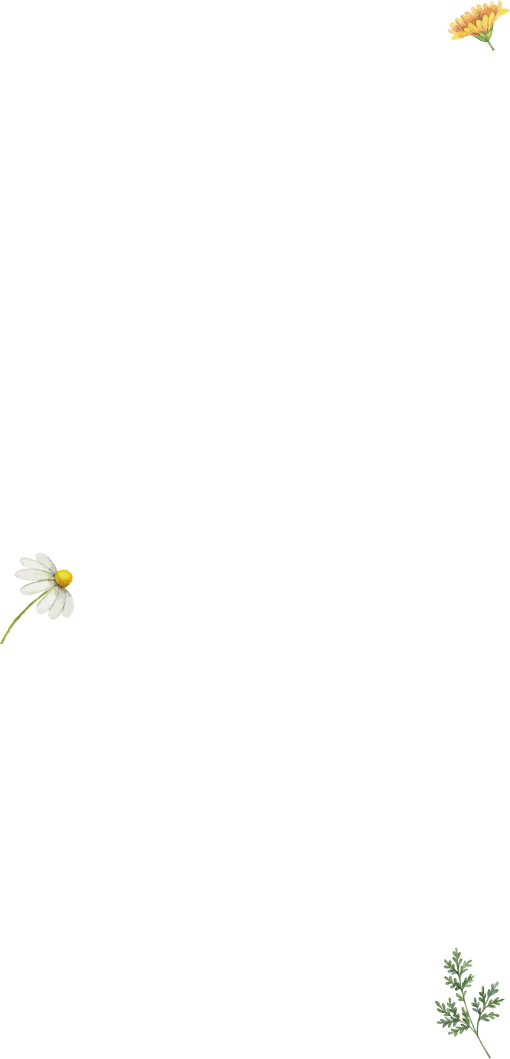
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ