かねがね明治政府はなぜ漢方を廃止して西洋医学を選んだのか疑問に思っていました。最近、石毛直道著『食事の文明論』(中公文庫)の以下の文章を読んでやっと腑に落ちました。
〈疫病の蔓延の予防をめぐって、医療活動の社会化を国家の仕事としなくてはならないことになり、19世紀の中頃からヨーロッパの医学は国家の医学となり、国家という強大な権力を背後にひかえた発言権をもつようになった。わが国においても明治時代になると早々に、医師の資格が免許制度という国家の管理下におかれるようになる。このさい西洋医学が国家の医学となり、漢方医学を国家の医学と認めなかった原因のひとつには、漢方医学が、「個人の病気だけをなおす」医学であり、「社会衛生」の医学としての性格を欠いていたことがあげられる。近代栄養学や医学からの、個人の食事に対する発言権は、このような背景をもつものである。〉
明治時代になると日本は日清戦争、日露戦争と外国との戦争に明けくれるようになりました。そのような時代では、国民一人ひとりの健康よりもいかに多くの兵隊を戦場に送れるかということが優先されるようになったと考えられます。当時の医学レベルでは個人の病気を治すのには漢方がすぐれていましたが、社会全体を対象とした場合は西洋医学、とくに公衆衛生的な考え方が必須でした。また、外科治療も西洋医学がすぐれていました。
漢方のなかで戦争に役立ちそうな処方は女神散の原法である安栄湯くらいなものでした。安栄湯は戦のさなか、敵と対して傷つき、血が出てめまいがした時に使ったそうですが、それほど知れられていません。田七人参という生薬は止血効果にすぐれ、刀傷を負ったときに創部に擦り込んだり飲んだりしたそうですが、これも限界があったでしょう。
それに対して西洋医学は外科的手法で戦いによる傷を手っ取り早く処理することができました。また、時代は下がりますが、第二次大戦中のアメリカ軍の一分隊をえがいたテレビドラマ『コンバット』では、衛生兵が傷ついて苦しむ兵隊にモルヒネを注射して、たちまちラクにさせていまうシーンが何度も見られました。東洋医学では鍼などを併用してもこんなに簡単には痛みはとれません。とれるとしても名人芸が必要です。
白川一郎著『島原大変』(文春文庫)に登場する若き漢方医師は、誰にも治せなかった藩主の病をメンタルな病気と見破り、甘麦大棗湯を処方して見事に治療し、名医と賞賛されました。ところが普賢岳の噴火で多くの住民が被害を被ったときには無能でした。気の良い町医者達がけが人の手足を切った張ったで活躍します。
ここで思い出したのが当院の郷久理事長です。郷久先生は平成5年に札幌医科大学から奥尻町に短期出張に行っていました。そこで出くわしたのが大地震と大津波。先生は創傷を負った人々を次から次と縫合して大活躍しました。郷久先生は自称、災害男で、昭和56年の夕張炭鉱大事故の際にも夕張に出張していて、すでに亡くなっている人と生きている人を分けて、生きている人の治療に当たるというノウハウを身につけていたため、奥尻でもリーダーシップをとったとのことでした。
郷久先生はすでに心身医学の長老ですが、後に東洋医学も勉強して東洋医学専門医となっています。身近にこんな凄い先生がいるなんて、今、気づきました。郷久先生は戦争時でも平和時でも使い物になるたぐいまれな医師なのです。
第253回 忙酔敬語 戦争と漢方

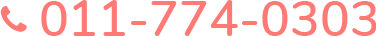




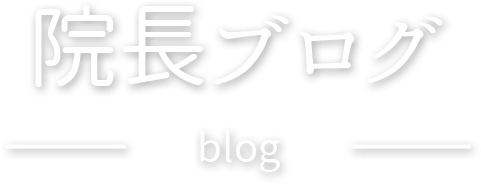




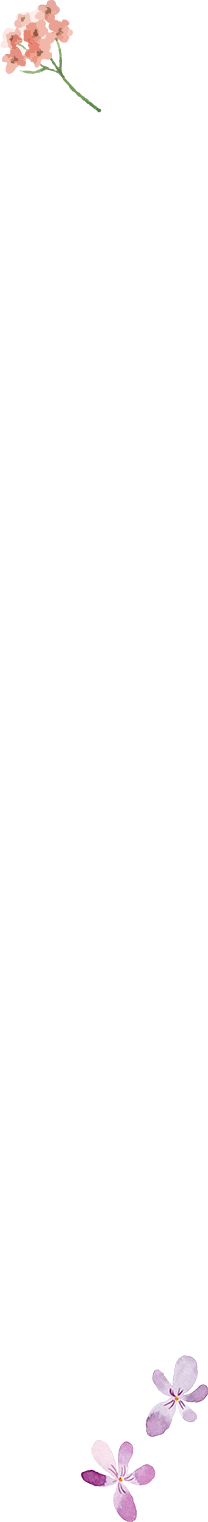
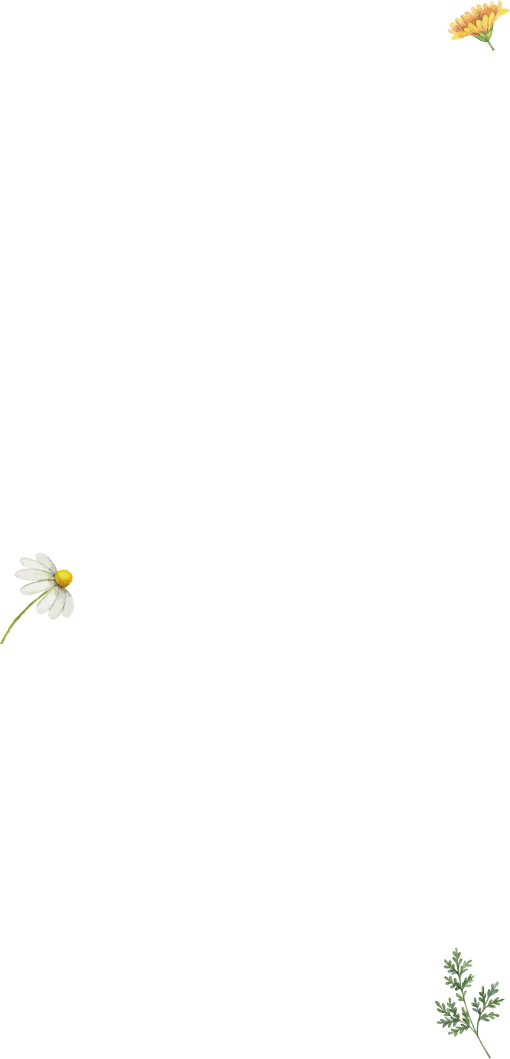
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ