当院では世間一般で言われている”看取り”は行っていません。しかし、産科診療をしていると流産という現実を避けて通ることはできません。このような状況に対して緩和ケアのスキルが応用できます(本当はスキルなんてチャライ言葉は使いたくないのですが、日本語では技能とか技術とか硬い感じになりしかたなく使いました)。
妊娠なかばまでもたなく亡くなってしまった赤ちゃんは、昔はお母さんに見せるのは精神上良くないと考え、すぐに遠ざけてしまったものです。当人の意志など確認せずに医療者や家族を含め回りの人間が勝手に解釈したのでした。当のお母さんの中には赤ちゃんに会いたいとウロウロと分娩室の回りを歩き回る人もいました。よけいな思い込みをしたもんだと今思い出しても胸が痛みます。
今では流産した赤ちゃんの体をきれいに拭いてタオルなどでくるんでお母さんの枕元に置いて面会してもらいます。もちろんお父さんも一緒。二人とも涙を流し、お母さんは「ゴメンね」と言いながらさらに涙を流します。昔はこの涙がマズイと考えたんですね。しかし、この涙はお母さんの心のわだかまりを洗い流す作用があり、その結果、悲しみを乗り越えてまた頑張ろうといった気持ちの入れ替えがスムーズに行わるようです。
要するに患者さんに対して基本的に秘め事はなし。しかし、何でもかんでも事実を説明すれば良いというものではありません。
昔は、多くの医師は進行癌の患者さんに対しては病名は告知しませんでした。それなのに札幌医科大学には当時、がん研内科があり、札幌市内には国立がんセンターがありました。そこで治療を受けていた患者さんは病名についてどのように説明されていたのでしょうかね。いつか確認しようと思っているうちにダラダラと現在に至ってしまいました。
北見赤十字病院に勤務していたとき、進行癌の患者さんを放射線科に紹介した際、放射線科の先生は「ちゃんと病名を説明してくれていないとやりにくいなあ」とこぼし、積極的に病名を告知してから放射線治療をしたため他のスタッフのヒンシュクを買っていました。しかし、患者さん自身がそれで精神的にダメージを受けたということを聞いたことはなく、病名を告知していない俺たちは出遅れているな、と自戒したものです。
死につながる病気に関しての告知は欧米から始められました。しかし、もともとヒューマニズムから行われたものではなかったようです。とくに訴訟社会のアメリカでは、病名が知らされなかったと告訴される例が多いため、しかたなく告知するようになりました。それ以前は進行癌の告知は90%されてなかったそうです。ところが告訴好きのアメリカでは、その後、年端もいかない子供に癌の告知をしたと親に訴えられたといった報道がありました。何だかややこしいなり行きですが、根本に思いやりの欠如といった寒々とした状況がうかがい知れます。
日本では癌の告知以外でも、あなたの余命は幾ばくです、と言った説明がよく行われていました。しかし、その幾ばくを過ぎてから、さらに何年もしかも元気に過ごしている例もあり、例外はあるものです。ですから希望をすててはいけません。
現在、緩和ケアは専門の施設で行われるようになり、若い研修医が”看取り”を経験することが少なくなりました。私は”看取り”は医の原点と考えているのでこの風潮が残念でなりません。
第231回 忙酔敬語 続々・看取り

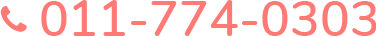




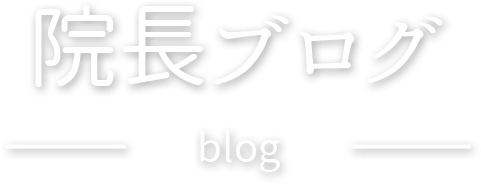




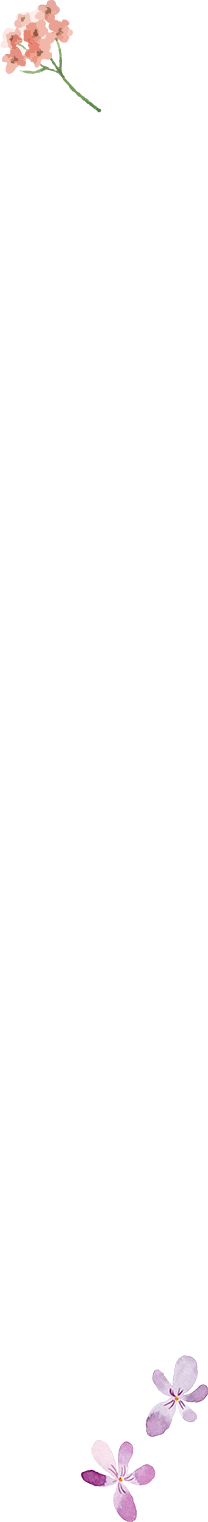
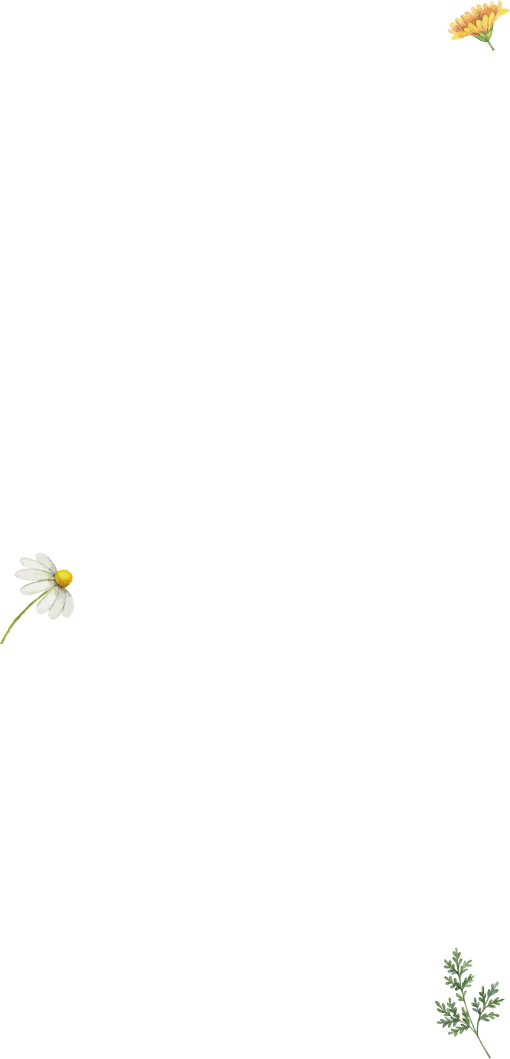
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ