物心がついた頃から死を恐れる子供でした。悪ガキに「死ーね」と言われるとウルウルとなる弱虫でした。どこから吹き込まれたのか人間の寿命は100年と信じていたので、小学生になって引き算が出来るようになると、「100引く7だからあと93年しか生きられない!」と悲観する始末でした。それが高校生になると途端にニヒリストになって、「いつ死んでもイイや」と考えるようになりました。でもこれは一時的。その後は医者になるまで死について深く考えることはありませんでした。
医者になって末期癌の患者さんに接するようになると、死は避けては通れなくなりました。人間は必ず死ぬ、だから死についての医学に関心を抱くようになりました。当時は調度、「死の臨床」の立ち上げの時代で、その後「ターミナルケア」、「緩和ケア」と穏やかな言い方に変貌していきました。
癌の患者さんのほとんどは(当たり前ですが)死にたくない人でした。ですから、当時は癌の患者さんに死を臭わせるような言い方は禁句で、ましてや本人に「余命は3か月です」なんて言うことは少なくとも私の回りではありえませんでした。したがって癌の告知もなし。しかし、病状が悪化すると個室に移動。これでほとんどの患者さんは「余命幾ばくもない」と察しました。中には全く口を閉ざしてしまった人もいました。今でも申し訳ないことをしたと悔やんでいます。もっとも下っ端の私には何の権限もありませんでしたが‥‥。でも、私なりに何か出来たかもしれません。
現在、「緩和ケア」が行き渡るようになり、癌による疼痛も克服されてきました。死を恐れるあまり、「ポックリと死ぬ」ことへの憧れが流行ったことがありましたが、最近では自分の人生をゆっくりと考えるために、「癌で死ぬ」ことをすすめる医師も現れました(中村仁一『大往生したけりゃ医療とかかわるな』)。実は私も「癌でゆっくり死にたい派」です。しかし、婦人科癌の最期はちょっと悲惨なので、しっかり健診を受けて別の癌で死ぬのをおすすめします。
さて、死にたくない人がいる一方、うつ病などのため、死にたい人もいます。実際に何度も餓死による自殺を試みて失敗した作家がいました(木谷恭介『死にたい老人』)。この人の場合は自分勝手で、うつ病でもないようで、その体験記を読んでも同情の念は湧いてこず、むしろ滑稽でした。しかし、念願かなって(?)この本が出版された翌年に85歳で心不全のため病院で亡くなりました。
「あと何年生きたいですか?」
死を恐れる外来の患者さんに私が時々問う言葉です。
「医者ともあろう者が何てヒドイ言い方をするんだろう!」
そう思われるのも当然ですが、自分もいずれは死ぬのは重々承知、自分は生きる人、あなたは死ぬ人といったニュアンスは全く含んではいない(つもりな)ので、患者さんが突き放されたといった反応を示したことはありません。そばについていたスタッフに確認したので間違いないと思います。死を恐れる患者さんの多くは死そのもの以外にも大きな不安をかかえています。お話をうかがった後で患者さんの肩や膝に手を置いて言います。
「あと20年は大丈夫ですよ、保証します!」
これで、ほとんどの患者さんはニッコリしてくれます。
第148回 忙酔敬語 あと何年生きたいですか?

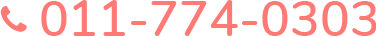




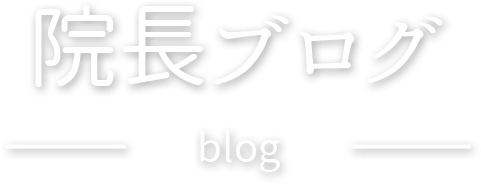




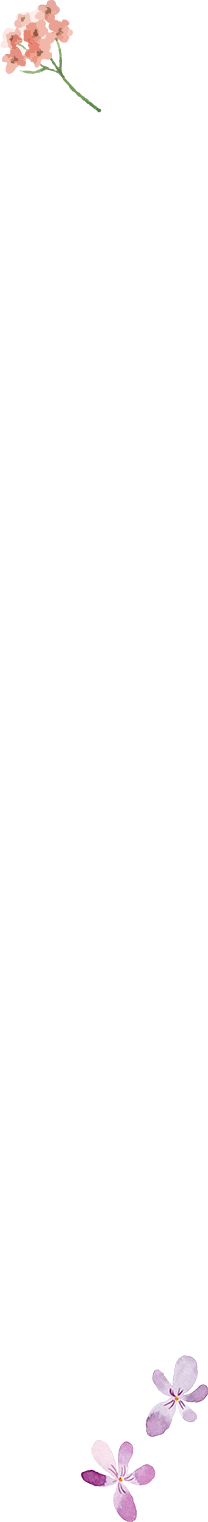
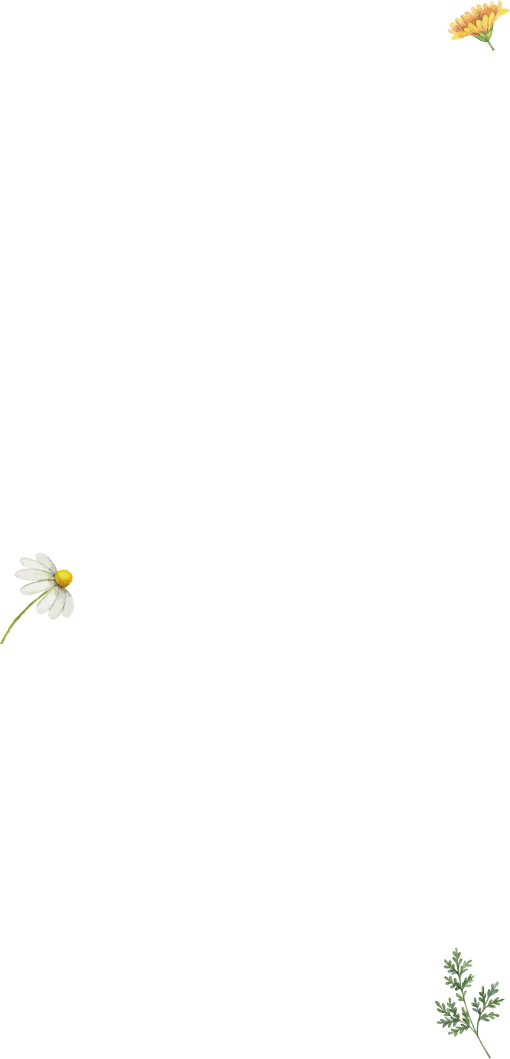
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ