外国の識者によると日本の医療の場ではユーモアが足りないそうです。上智大学名誉教授のアルフォンス・デーケン先生は死生学がご専門で、講演の度に自己紹介として「私鉄(死哲)のデーケンです」とまず聴衆の笑いをとります。
人が死ぬか生きるかという時にユーモアを発揮するのは難しいことですが、私も産婦人科教室に入局して早々、やらざるを得なくなったことがありました。特殊な絨毛癌の患者さんがいました。当時の文献では余命はわずか6か月以内とのこと。さいわい抗がん剤が効いて回復傾向にありました。
日中の勤務が終わり、ふらっと患者さんの様子を見に行きました。30歳になったばかりの女性で、頭の回転が早く新入医局員の私をよくからかっては喜んでいました。
「先生たちはどうせ何人も患者を死なせて腕を上げていくんでしょ」
とっさの言葉に私はたじろぎました。ありきたりの返事ではダメだと思いました。
「そのとおり。まず、○○さんに死んでもらおうかな」
きわどいジョークは通じ、お互いに笑ってすますことが出来ました。しかし、部屋を出た後、私の心は疲労困憊し涙があふれ出ました。人生でこんなに緊張したのは初めてでした。患者さんは結局完治しましたが強烈な体験でした。
精神科医で作家でもある、なだいなださんは、フランスに留学したとき、陪席させてもらった教授が若い女性を診て、「おう、何と見事な胸であろうか」と言ったのでビックリしたと書いていました。「日本ではこんなことを言う医者はまずないだろう」と思ったそうです。
私は学生の時分、柔道部の先輩の丸山淳士先生(現、五輪橋病院)が勤務している日高門別の町立病院に研修に行きました。当時から丸山先生はキツイ冗談を飛ばしては患者さんやまわりのスタッフを笑わせていました。この体験がインプリンティング(刷り込み)となり、私は診療の場では患者さんを笑わせなければいけないと動機付けされました。
産婦人科に入局したとき、まず婦人科で研修させられました。本当は産科をやりたかったので、お産のときは何も出来ないのにちょくちょく分娩室を訪れました。同期の早川先生が頑張っていました。私は産婦さんの枕元で「そんなに余計な力を入れたら顔がゆがむぞ」とか何とか丸山流のジョークで励ましました。その産婦さんは退院するとき、わざわざ私にお礼の品(紅茶セット)を持って挨拶に来ました。
「先生のおかげで頑張れました」。早川先生は怒りました。
「佐野は口ばっかりなのにオレには何もくれなかった」。
丸山先生のジョークは天然物で、その後、テレビやラジオでも活躍されています。7年ほど前に手術の手伝いをお願いしたところ、麻酔が効いていざ手術を始めようとしたとき、患者さんの顔をのぞき込んで言いました。
「何か言い残すことはないか、貯金通帳の場所とか」
これにはあらためて驚きました。とてもかなわないなあ。
笑いは健康に良いとされ、老人介護施設でもインストラクターが訪れて、お年寄りを相手に「笑うと交感神経を静めて免疫を高めます。さあ、笑いましょう、ワッハッハ」とやっているのを見ましたが、自然の流れでないとダメだなと思ったことでした。
第141回 忙酔敬語 診療と笑い

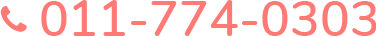




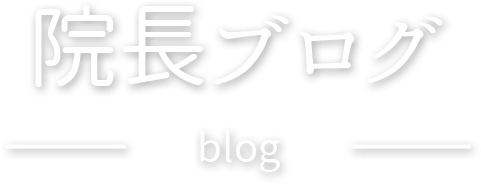




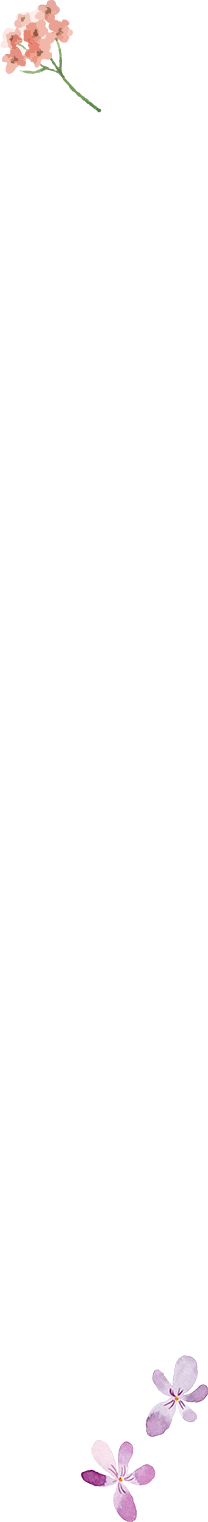
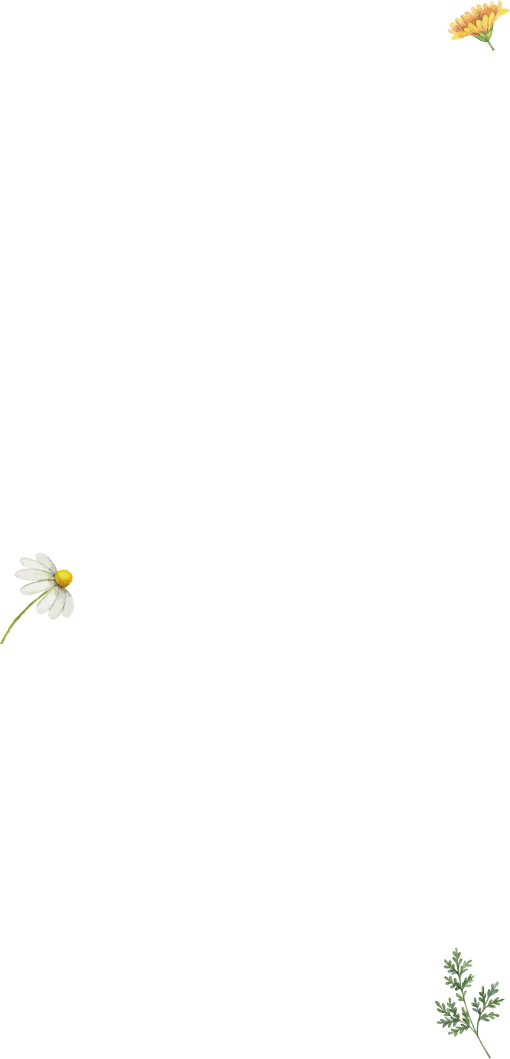
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ