12月5日の「日医ニュース」に掲載された東京の澁井展子先生の「母と子の絆」というエッセイの抜粋です。
1956年、フランスのマルセル・ジーパーが、栄養不良が子供の知能に与える研究をするためにアフリカに調査に入り、画期的発見をした。そこには予想とは違い、今までの世界の何処においても遭遇したことのない、早熟で賢い、知能の進んだ乳幼児が存在していた。ウガンダの母親は、陣痛が始まると自分一人で子どもを出産し、後始末を済ませ、産後一時間ほどで、生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて親類縁者に披露していた。新生児は、母親の首から吊された三角巾のような帯の中に、おしめも付けずに裸のまま収められ、四六時中、母親の胸から離れることなく育てられる。赤ちゃんは欲しくなればいつでも乳を飲むことが出来、母親は吊り布一枚を隔てた肌の触れ合いから、赤ちゃんの気持ちをいつも感じ取り、何をして欲しいかを即座に理解することが可能なのである。赤ちゃんは、敏感で注意深く、静かに満ち足りていて、驚くほど長い時間、目を覚ましていた。そしてほとんど泣くことがなかった。なぜなら、赤ちゃんの要求が泣いて訴えるほどに膨らむ前に、母親はその思いが何かを察知し、それに応えてあげることが出来るからである。母親は赤ちゃんのどんな仕草も見逃さず、子どもの全ての思いに応えるのである。驚くことに、こうして、育てられたウガンダの赤ちゃんは、生後二日目には、前腕を支えてあげるだけで、まっすぐにお座りが出来、背中をピンと伸ばしていたそうである。首の座りも早く、目は自分の意志と知能とで、母親をしっかりと見据えていた。いつも機嫌良くにこにこ笑いながら。その後、ウガンダにも近代的な分娩施設が造られ、自然分娩・自宅分娩から、人工分娩・産院分娩に変わった。そして産院で人工分娩によって生まれ、吊り帯で育てられなくなった赤ちゃんには、前述した「ウガンダの赤ちゃん」の素晴らしい特徴は、ほとんど消えてしまったそうである。ウガンダの赤ちゃんの育て方が、そのまま日本で通用するはずもないが、出産を自力でなし遂げ、その後の一年間、赤ちゃんを24時間片時も離さずに抱き、慈しみながら育てた母親がいて、その赤ちゃんがユニークな発達を遂げたことは事実である。
第8回のブログで「赤ちゃんの泣く理由」について偉そうなことを書きましたが、昔のウガンダのお母さんは赤ちゃんが泣く前に赤ちゃんの思いを察することが出来たんですね。日本でも健康な家族間ではお互いに相手の気持ちを察することが出来ました。突飛な例ですが、平安末期に書かれた『今昔物語』に、新たな勢力として台頭してきた武士の親子の絆の強さを紹介した「馬盗人」の話があります。父親が名馬を手に入れた事を知った若武者が父に挨拶に行くと、父は息子が何も言う前に気持ちを察して「お前にあの馬をくれてやろう」と言います。『今昔物語』の入門書を書いた今東光が「こんな親だったら俺もグレなくて済んだのに」と語っていました。第40回のブログで「仏語圏アフリカご一行様」を紹介しました。出来るだけ上から目線でないように努めましたが、やはり上から目線でした。この「ウガンダの赤ちゃん」の記事を読んで、来年は逆にアフリカの自然な子育てについて学ぼうと思いました。

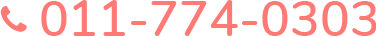




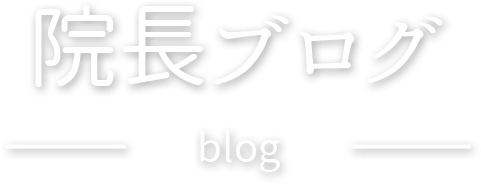




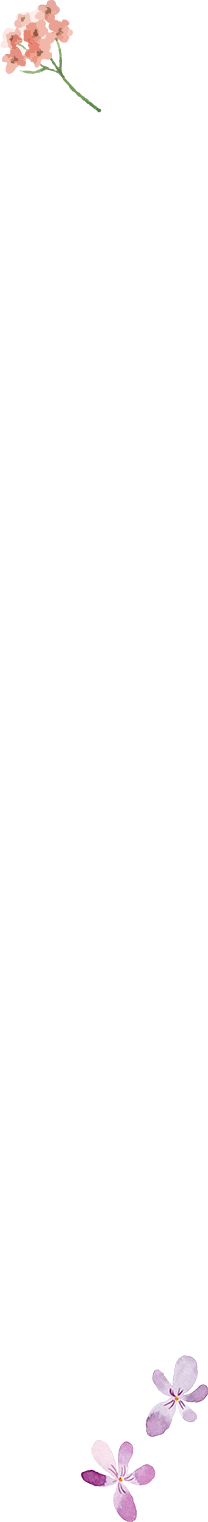
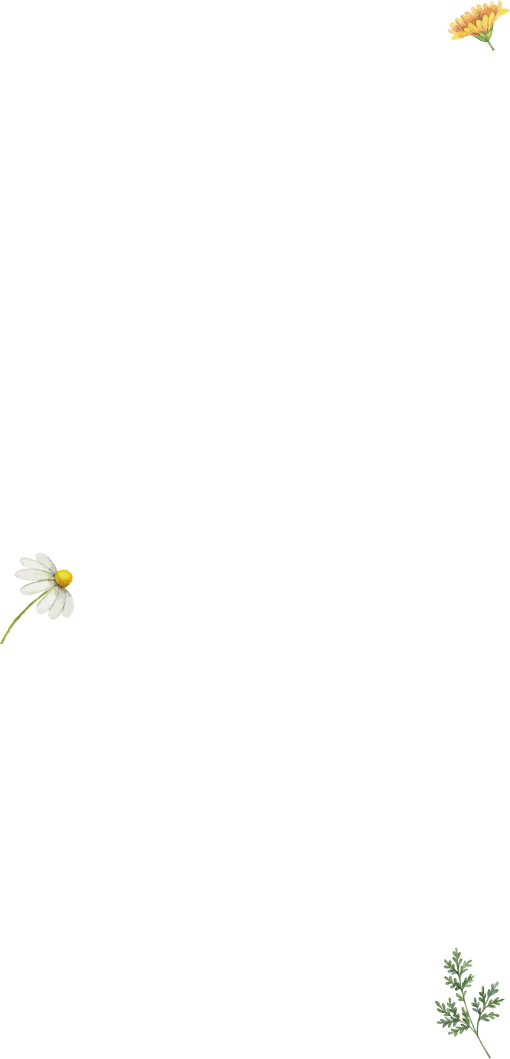
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ