久しぶりに友人とゆっくりと積もる話をしようと年末に彼の自宅へ遊びに行きました。出迎えたのは可愛らしい小型犬。人なつっこく私にまとわりついたあげく、膝の上に頭をのせて眠ってしまいました。これには友人もビックリして「良い人だって分かるんだね」と感心しきり。でも、これって買いかぶりです。私は本来、動物は嫌いではないけれどムツゴロウ先生にははるかにおよばず、もし噛みついてきたら蹴飛ばす覚悟でいる潜在的に危険な男です。犬が安心したのは友人が私に対して好意を示しているのを感じとったからだと思います。主従関係がしっかり躾けられている犬にとってご主人様の行動がすべて。その証拠に友人が寝ている姿を写真に撮ろうとした瞬間、気配を察してムクッと目を開けてジッと友人の様子を見つめました。そして安心してまた頭を膝にのせました。私よりもご主人様が第一だと分かりました。
東洋医学では望診といって、患者さんを見た瞬間の全体の印象を大事にします。私の師匠の下田先生は望診で八割診断できると言っていますが、私も問診票を見た後なら七割くらい見当がつきます。本当かなと思われるかもしれませんが名人芸ではありません。動物同士の伝達に言葉は必要ありません。もちろん、ワンワン、ニャンニャンとか吠えたり鳴いたりしますが、これは赤ちゃんがオギャーと泣くのと同じで言語ではありません。
望診はあくまでも患者さんを全体的に一瞥した印象ですが、犬の場合はさらに臭いや声の調子が判断材料として加わります。むしろこちらの方が大きな位置を占めるかもしれません。臭いや声の調子による診察を東洋医学では聞診(ぶんしん)と言います。その他、問診(これは西洋医学とほぼ同じ)、切診(腹診、脈診など患者さんの体に触れること)があり、これをトータルして四診と言います。すなわち犬は問診以外、望診、聞診、切診と東洋医学の重要な診断のほとんどを一瞬にして行っているのです。
スコット・スターン、アダム・シーフー、ダンアン・オールトカーム編 竹本毅訳『考える技術』(日経BP社)に疲労がとれないという症例が掲載されていました。小学校の先生でMBIが35。米国白人女性なので身長は多分165cmくらいでしょうか。そうなると体重は95kg以上です。うつ病やホルモン疾患などさんざん検討したあげく、結局、肥満による睡眠障害と診断されました。そして、対策の一つが仰向け寝を防止するためリュックを背負って寝るというヘンテコな方法。米国ではこの程度の肥満は珍しくはありませんが、診察室に入った瞬間に勘が働かなかったんでしょうかね。また、そもそも肥満に至った契機を確認し、肥満を解消しなければ根本的な解決にはならないと思いました。
東洋医学的な四診もやり過ぎは禁物です。「痛くもない腹を探られる」という言葉があります。もともと、あらぬ疑いをかけられる不快感を意味していますが、望診、問診、聞診で見当がついたら切診(腹診)まで必要ないことが窺われる言葉でもあります。
内科研修医のために書かれた岡田定・大蔵暢編『内科レジデントの常識 非常識』(三輪書店)の第1章「21の超常識」の始めが「1.客観的なデーターだけに頼らず、直感やセンスを大切にせよ!」という言葉。何だか『スターウォーズ エピソード4』でデススターに突っ込むルークに対して亡きオビ=ワンの霊が「計器に頼るな、フォースを信じろ」とささやくシーンを思い出しませんか? だんだんアヤシゲになってきましたが、フォース=犬のセンスと理解して頂けるでしょうか。自然界ではこれが超常識です。
第211回 忙酔敬語 臨床における直感は犬に学べ

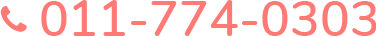




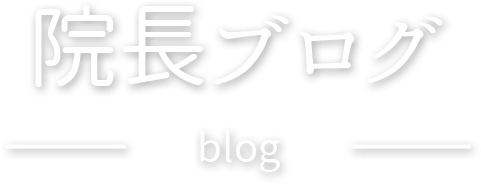




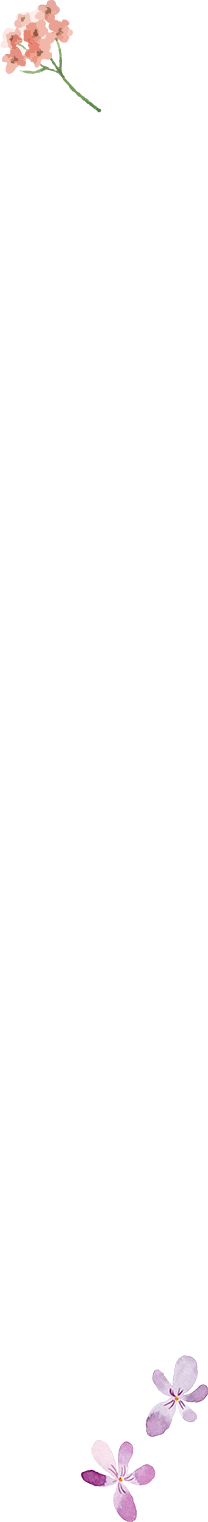
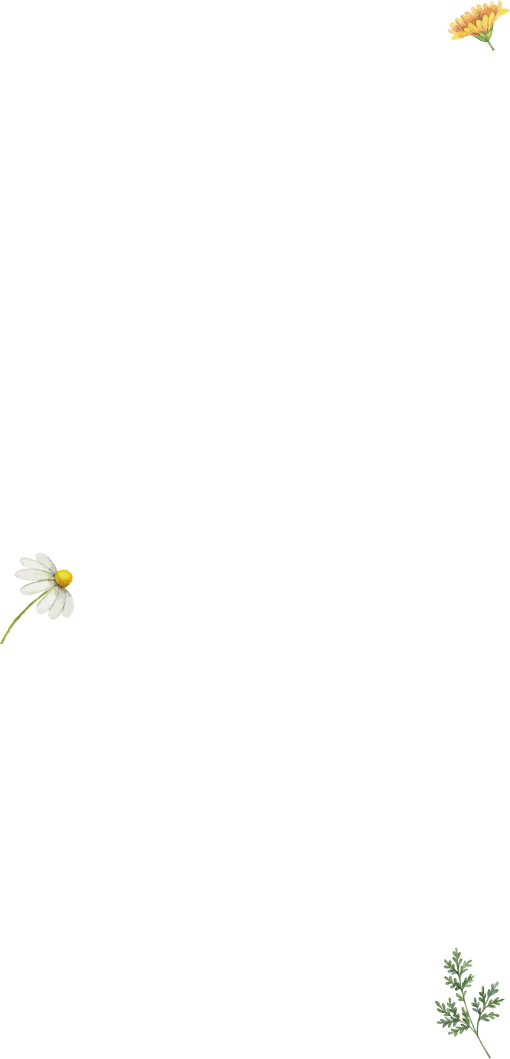
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ