「23番の漢方をください」
ひさしぶりに受診した患者さんが言いました。
「それじゃあ、囚人番号みたいですね。ちゃんと当帰芍薬散と言ってください。愛がこもっていないと効く薬も効きませんよ」
当帰芍薬散は当帰、芍薬、川芎、沢瀉、茯苓、朮で構成され、いわゆる貧血、痛み、むくみ、冷えが目標になります。「当芍散」と略して言う場合もありますが、患者さんでここまで精通した人は見たことがありません。
その他、葛根湯、桂枝茯苓丸など1800年ほど前につられた漢方薬は、主な構成生薬を処方名に使われています。出典は『傷寒論』と『金匱要略』です。
なかでも苓甘姜味辛夏仁湯は、茯苓、甘草、乾姜、五味子、細辛、半夏、杏仁、といったすべての構成生薬の一字をならべただけで実に芸のない長い処方名で、覚えるのに1か月もかかり、それこそ作者の愛が感じられず不憫に思ったものです。冷えて、くしゃみ、鼻水の出る患者さんには即効するのですが、私の師匠の下田先生もめったに使わないと『臨床薬理の立場からの処方解説』に書かれており、ますます不憫に思いました。これは119番と番号で呼ばれても仕方がないでしょう。いよいよもって不憫なものです。
それに対して同じように鼻風邪に使用される小青竜湯は、立派な名前をつけられ大きな顔をしています。10年ほど前に私は『産婦人科漢方のあゆみNo.25』に「苓甘姜味辛夏仁湯を中心とした妊婦および褥婦の鼻炎の治療」という論文を書きました。その考察で「処方名からしても単に構成生薬をならべただけの苓甘姜味辛夏仁湯よりも、青竜という春の湧水とも麻黄の青さが由来ともされる小青竜湯のほうが古代の治療者の思い入れが強かったのではないかと考える」と独断と偏見に満ちた言葉で結んでしまいました。
ところが、今年の泊まりがけの勉強会で、『傷寒論』や『金匱要略』以前に作られた漢方薬には生薬の名前ではなく呪術的な思いが込められていることを知りました。中国には伝説上の神獣として四神がいて、青竜は東方を守り、白虎は西方を守り、朱雀は南方を守り、玄武(真武)は北方を守ります。それらは古代の処方名に採用され、(小、大)青竜湯の他に白虎湯、真武湯があります。こういった漢方はとくに祈りを込めて「真武湯をください」とお申し付けください。間違っても番号で言ってはいけません。
越婢湯は『金匱要略』に掲載されている漢方薬です。一説によると著者の張仲景が越国の婢より得たために越婢湯を名づけられたと言われています。または「婢」は本当は体内の機能の総称である「脾」で、そことどまるべき水分がその部位を越えて汗やむくみなどの症状を引き起こす、それを正常にするのが本処方の目的であり、越「脾」湯が正しいと言っている先生もいます。エキス剤では朮を加えた越脾加朮湯が医療用の漢方薬として採用されてします。ほてりや汗などの更年期症状にも使われています。このように越脾加朮湯の名前の出目ははっきりしないので、28番と言ってもさしつかえないでしょう。
一方、日本で工夫された処方は、化膿性皮膚疾患に用いられる十味敗毒湯、打ち身に効く治打撲一方、子どもの頭の湿疹に使う治頭瘡一方などと実に分かりやすい。漢方の理論を知らなくても、はずれはほとんどありありません。自然哲学的な理論にこだわる中国漢方よりも実用的で好感が持てます。
第362回 忙酔敬語 漢方薬を番号で呼ばないで

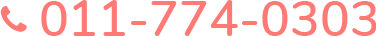




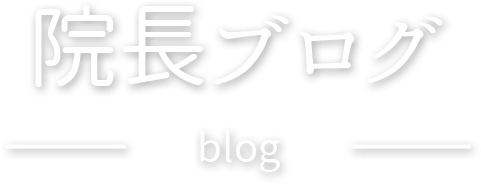



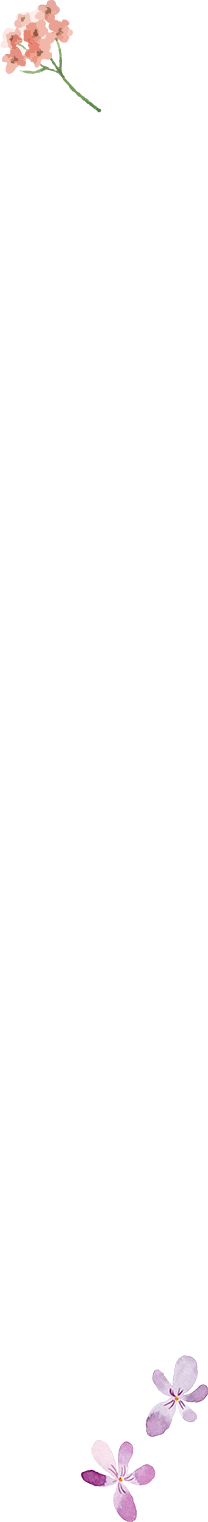
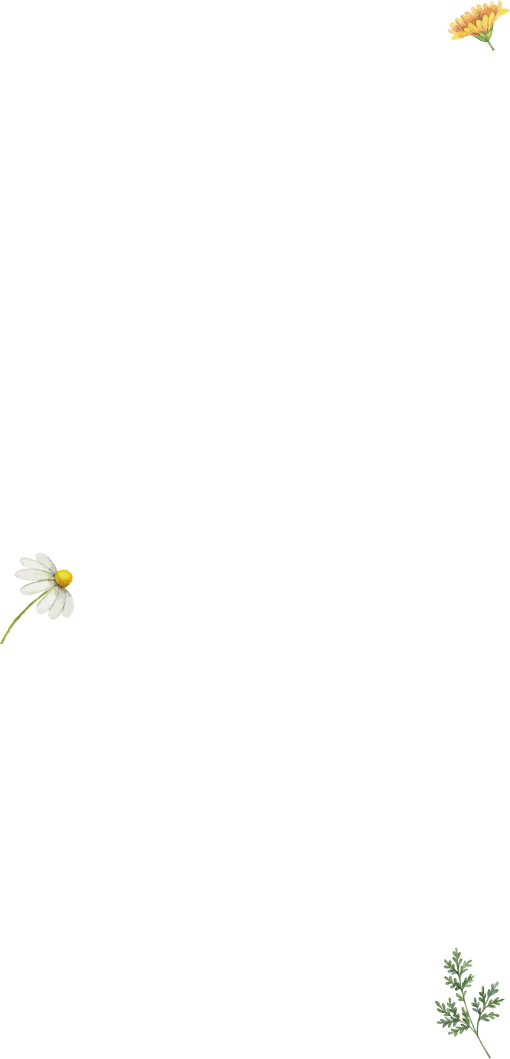
 〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
〒002-0856 北海道札幌市北区屯田6条2丁目11-1
 トップページ
トップページ